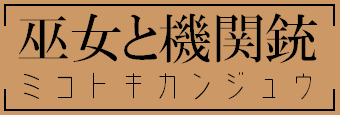短々編07 - 健全な魔術
あなたはとある人物の知識を頼る為にここまでやって来た。ここは、あなたが頻繁に訪れる場所では無かった為、入口に立った時には出迎えてくれたメイドから妙な顔をされたものである。だが、訪問の意図を話すとメイドは快く通してくれた。そして、あなたを丁寧に目的の場所まで案内してくれると言うのである。
「今日は、まだあの人は来ていないようですよ」
「あの人? 一体、誰の事かしら?」
先行するメイドの背中を見ながらあなたは惚けたような口調で返事をする。すると、メイドは少々嫌味を込めたような、あなたに向かって言ったのか独り言なのか分からないような曖昧な口調で言った。
「あら、あなただったら分かっているはずだけれど……」
どうやら目の前に居るメイドは、あなたはいつも“誰か”を追いかけ、“誰か”と一緒に居ると思っているらしい。あなたはその“誰か”という存在に大体の見当がついていたが、ここで相手の調子に乗ってしまうのも馬鹿馬鹿しいと考えて、しらを切る事にした。
「さあ? 分からないわ」
するとメイドは、あなたの口調から何かを悟ったのか「あら、そう」と何か含んだ曖昧な口調(どうやら、このメイドは曖昧な口調での返事が得意らしい)で返事をした。それからあなた達は会話を交わす事も無く、目的の場所まで歩き続けた。長い長い廊下に足音だけが響き渡るのは、まるで誰も居ないオペラハウスの舞台を歩いているかのようだとあなたは感じる。
「少し待っていてちょうだいね」
目的の扉の前まで行くと、メイドはあなたを止めた。そして、目の前の重そうな扉(相当な厚さがありそうだ、実際に重い扉だろう)をノックした。あなたはノックのすぐ後に、扉の内側から誰かがくぐもった小さな声で返事をするのを聞いた。そして扉がゆっくり開くのを、あなたはじっと見ている。扉の中から顔を出したのは、髪の赤い一人の従者であった。
ここまで案内をしてくれたメイドが簡潔に取り次ぎ、あなたの案内を従者に引き渡した。従者は「どうぞ」と一言だけ言って(先程までのメイドとは違い、この従者は愛想が良かった)、あなたを館内へ案内してくれた。
あなたが後ろを振り返ると、メイドが丁寧にゆっくりと扉を閉めているのが見えた。愛想は良くないが、いつ見ても動きだけは熟練の洗練された物だとあなたは思う。次に、あなたは室内の光景に目を奪われる事になる。そこには何時見ても圧倒される光景があった。ビブリオマニアも行き着くとここまでになる物なのかと、あなたは関心とも畏怖ともつかない感情で見えない天井を見上げる。見上げても見上げても、見えるのはどこまでも続く本の背表紙ばかりである。
あなたは貴重な本が文字通り山のようにあるのを見て、今後は“誰か”がここへ通い詰めて毎度のように本を大量に持ってくる行為に対しては、ある程度の理解を示す事にした。
頭上に気を取られていたあなたは、いつの間にか止まっていた従者にぶつかりそうになって危い所で足を止めた。幸いぶつかりはしなかったが、突然足を止めた為に見た目はかなり無様であったに違いない。だが、あなたはその光景を誰にも見られていない事に気付いて胸を撫で下ろす。雑多に本が積まれた机(あまりに本の量の多い為、机自体が本で構成されているのではないかと見間違うほどだ)に座っているその人は眼前の本を読む事に夢中で、あなた達が近づいてきた事すら気付いていないようであった。
「失礼いたします。お客様です」
従者は静かに、だがはっきりと声を発した。それを聞くと本に埋もれていた愛書家が、神経質そうな動作でこちらを向いた。あなたは久しぶりに見るその顔に、月並みな挨拶をせずにはいられない。
「どうも、会うのは久しぶりね貴女」
あなたの顔を見た愛書家は一瞬だけ意外そうな顔をするも、すぐに元の味気の無い無表情に戻して視線を本へと向けた。それを見たあなたは少しだけ落胆する。だが、それを言葉には出さない。そして、相手も何も言わない。
ふとあなたは、先程まで居たはずの従者は居なくなって、いつの間にか椅子と机が用意されていた事に気付く。机は黒に近い焦げ茶色の木で出来た四角い物で、脚部は猫の脚のように丸められていた。椅子の方は背もたれに装飾の施された豪華な物で、座面と背もたれの中央部には真紅の布が張られていた。
あなたは用意された椅子の内の一脚に幾分か見た目が良く見えるように腰をかけると、無駄に大げさな仕草で脚を組んでから、じっと愛書家の方を見てみる事にする。愛書家はそれに気付いているのだろうが、あえて何も言わないようだった。あなたは愛書家をこのまま見つめていても仕方が無いので、自分から行動を起こす事にする。
「ねえ、今日は貴女に聞きたい事があって来たのよ」
愛書家はあなたの言葉を聞くと、眼前の本から眼を上げてあなたをじっと見た。あなたはその視線で、自らの顔に穴でも開くのではないかと思ったほどである。そして、ようやく愛書家は口を開く。
「珍しいわね。で、何を聞きたいの?」
愛書家からの質問を受けて、あなたは少し間を置いてから用意していた言葉を口にする。
「恋愛の魔術について」
あなたの発言を聞いて愛書家は驚いたように目を見開いた後、困惑と疑惑の混ざった妙な表情を浮かべた。そんな表情を見て、あなたは説明が足りなかったのではないかと考えて補足の一言を付け足す事にした。
「一度離れた相手の気持ちを、再びこちらへ向ける為の魔術について教えて欲しいの」
愛書家は先程の一言に余程興味をひかれたらしい。今まで座っていた椅子からおもむろに立ち上がると、ほくそ笑むかのような表情を浮かべながらあなたの傍まで来て空いている椅子に腰をかけた。
「魔法使いのあなたが、わざわざ魔法を教わりにここへ来たって言うの?」
あなたは愛書家の発言を聞いて、それは尤もな事だと感じた。
「そうね、あなたは私に媚薬の作り方でも教えて欲しいのかしら?」
「違うわよ。そんなのじゃなくて、もっと健全な物よ」
健全な物と言った後にあなたは思う。果たして、魔術に健全な物などあるのだろうか。そもそも、術で人の気持ちを惹こうだなんて健全ではない。だけれど、そんな疑問など今のあなたにとってはどうでも良い物であった。あなたは、その考えを頭の中で乱暴に丸めると何処かへ放ってしまう。
「健全な物、ね」
笑うのをとっくに止めた愛書家はぽつりと呟くと、手馴れた手つきで従者を呼んだ。そして、少し離れた暗がりから現れた従者に本と紅茶を持ってくるように指示をした。あなたはその光景を羨ましく思ったが、自分でも同じような事が出来るじゃないかとすぐに開き直る。ただ、あなたの抱えている従者には少しばかり“人間味”という物が足りないのが残念ではあったが。
「で、どうして私に聞きに来たの?事の流れを教えてちょうだい」
愛書家はあなたに事情を説明しろと言う。だが、あなたは事情を話したくなかった。
「そうね、何故かしらね。まあ、そんなのはどうでも良いじゃない」
あなたは適当にごまかそうとしたが、目の前に居る愛書家は簡単な相手では無い事を知っていた。だから、あなたはこんな事を言っても駄目なのは分かっている。
「そうなの?じゃあ、私も教える必要は無いわね。お帰りはあちらよ」
愛書家はあなたがやって来た方向を指差すと、冷たい口調で言い放った。無論、あなたはすぐに帰りたくは無い。そこで、少々芝居掛かったような仕方が無いといった素振りを見せた後、あなたはゆっくりと口を開く。
「分かったわよ、ちゃんと言うからそんな事は言わないでちょうだい」
あなたはここで言葉を切ってわざと間を作る事にした。十分に間を置いてからあなたは「最近、とある“誰か”が自分にとても冷たい」という話を努めて悩ましげな口調に聞こえるように言う。表情もなるべく深刻そうに見えるようにする。すると、あなたのやり方が功を奏したのだろうか、愛書家は溜息をつくと「納得できない所もある(愛書家の表情を見ると納得できない事だらけのようだ)けれどあなたに協力する」と約束してくれた。
用意されていた四角い机の上が持って来た本で埋まり、ティーポットの置き場に困りながらあなたは紅茶をカップに注いだ。もうそろそろ何杯目か忘れる頃で、あなたは既にこれが何杯目なのか分からなくなっていた。ポットが空になりそうになると愛書家の従者がすかさず交換に来る為、何個のポットを空にしたのかもあなたは見当がつかなくなっていた。
あなたは視線をゆっくりとあげて、愛書家の顔を覗いてみる事にする。大きな本の影から眼だけが見えていて、愛書家の鋭い眼は紙の上の文字を追う為に忙しなく動いていた。
「どう? 見つかった?」
あなたは愛書家に進行状況を尋ねた。
「ええ、見つかったわ。単純な物から手間が掛かる物まで色々あるわよ」
愛書家はあなたに一冊の重そうな本を手渡す。あなたはその本を開いて内容を読む振りをしながら、愛書家に話しかける事にした。
「色々あるわね。貴女のお勧めは何?」
「お勧め?さあ、分からないわ」
あなたは、愛書家の返答を聞いてもしつこく聞き返そうとは思わなかった。なぜならそれは、その答えを聞く事があなたの目的ではないからである。むしろ、あなたの目的は今現在すでに達成していると言っても良い状況である。すると、愛書家はあなたに向かって何かを言ったらしい。だが、言葉を聞きそびれてしまったあなたは、何を言ったのか聞き返してみる事にする。
「ごめんなさい、聞いていなかったわ。一体、なに?」
「だから…さっきあなたが言っていた、こんな事を聞きに来た理由についてよ。ある人が最近あなたに冷たいって話。本当なのかどうなのか、私は何処か引っ掛かるのよ」
「あの話が本当かどうか? そんなの決まっているわ、嘘を言ってどうなるの?」
言葉の冷静さとは裏腹に、あなたは内心焦っていた。このままでは自らの企みがばれてしまうのではないかと、不安を覚えたからだ。
「貴女がそんな悩みを私に打ち明ける事なんて、今までに無かったから。だから、不自然に感じたのよね」
「まあ、確かに今まで誰にも相談しなかったわよ。今回が初めて」
あなたの言葉を聞いた愛書家は更に首をひねった。それはもう、首が折れそうな程(実際はそこまで急激な動きではないが)の勢いで。
「待って、何で私を選んだのよ? 他にも相談できる人は沢山居るでしょう?」
「それは……偶然よ」
「へぇ、偶然で私は選ばれたのね。分かったわ」
愛書家の発言からは明らかに納得しきれていない時の声色が聞き取れたが、あなたはそれ以上その話を続けたくはない。そろそろ潮時だと感じたあなたは、持っていた本を勢い良く閉じた際の予想以上に大きな音に驚きながらも、本を机に置いてから気丈を装って椅子から立ち上がる。
「そろそろ失礼するわ。美味しい紅茶をごちそうさま」
突然、帰ると言い出したあなたを怪訝な目で見ている愛書家とは、目を合わせないようにしてあなたは踵を返す。すると背後から言葉が飛んできた。
「ねえ、あなた。もし良かったら、その本を貸してあげるわよ」
その愛書家の提案に、あなたは驚くと共に喜びを感じる。だが、それを顔に出さないように気をつけつつあなたは再び踵を返す。
「良いのかしら? じゃあ、お言葉に甘えて借りて行くわね。いつ返せば良い?」
「そうね…いつでも良いわよ。返してもらえるならば」
あなたが愛書家の顔をふと見ると、再びほくそ笑む様な表情を浮かべている事に気付く。その顔を見たあなたは、目の前に居る人物に全てを見透かされたような感覚に陥ってしまった。まるで頼りない小舟の上に立っているかのような錯覚に襲われたあなたは、足元がふらつかない様に意識を集中させる事で精一杯である。
「どうしたの? 具合でも悪い?」
あなたは愛書家の言葉で小舟の上から陸に上がる事が出来た。ただ、愛書家の口角は先程よりも上がっているようにあなたには感じられた。
「ええ、大丈夫……ありがとう。またいつか、お邪魔するわね」
あなたは力の抜けた手を気持ちばかり振ってから愛書家に背を向ける。あなたが歩み始めると、後ろから愛書家の声が霧に消え行く霧笛の音のように微かに聞こえてきた。
「じゃあ、またいつか」
◆ ◆
机の上に残されたのは、中身が少ししか残っていないティーポットと数々の本の山、そして飲みかけの紅茶の入ったカップが二つ。そして、そんな机の僅かな空間に本を開いて頬杖を突きながら考え込むように座って居る魔女が一人。その目線は先程まで居た一人の魔法使いが座っていた椅子に向けられていた。
「パチュリー様、机の上を片付けてもよろしいですか?」
小悪魔の声が、本の山の向こうからはっきりと聞こえた。
「ええ、良いわよ。片付けてちょうだい」
パチュリーは考えていた。何故、彼女はここへ来たのだろうかと。しかし、納得の行く答えを導く事は出来ないでいた。
「ねえ、こあ……何が目的で彼女はここへ来たのかしら?彼女は魔法使いだから、魔法に関しての知識なら不足は無いはず。それなのに突然、私の所へやって来て魔術を…しかも、恋愛に関する魔術を教えてくれ、だなんて言い出すのかしら…意味がわからない…」
小悪魔は机の上を手際良く片付けながらパチュリーの話を聞いていた。そして、にっこりと微笑むとトゲの無い優しい口調で言うのだった。
「そうですね……もしかしたら、彼女はパチュリー様とお話がしたかっただけなのかもしれませんよ?」
パチュリーは小悪魔の言葉を聞いて呆然とした。そして、苦笑いを浮かべると「まさか」と一言呟いて視線を手元の本へ落した。
-終-