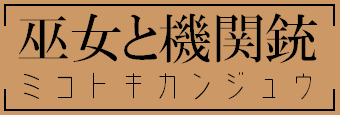短々編08 - 残留物の後遺症
意識を取り戻して最初に視界に入ってきたのは、大きく歪んだ長い針と短い針、そして忙しなく動き続ける細い針だった。私はその三本の針を、混濁する意識の中でただ無機質に目の前の物を捉え続けるような視線で眺めていた。何故、細い針は忙しなく動いているのに、長い針は少しずつしか動かないのだろうかと考えているうちに、その針達は時計の一部である事に私は感付く。普段ならばこんな下らない考えは浮かんできた瞬間に沈めてしまう物だけれど、この時ばかりはそうは行かなかった。私の意識は重い水の上に不安定に浮いているようで実に頼りなく、自らの身体は絡操り人形のように硬くなってしまっていて満足に動かせる自信が無かった。身体の中心部に鉛でも注がれたように身体が重く、頭は中身が凝固してしまったかのように感じられた。つまり、身体中のあちこちにいつもより重い何かを詰め込まれているかのような、そんな感覚が私の全身を包んでいたのである。
そんな状態で私は動き続ける時計の針を凝視していたのだけれど、ふとした拍子に身体を起こさなくてはならないと考えた。おかしな話だけど、この時になって初めて私は自らが身体を横たえている事に気がついたのである。しかし、重りのような物が一杯に詰まっている身体を動かす為のは一苦労だった。それでも何とかして上半身を起こす事が出来た私は、回り続ける視界に酔いそうになりながらも上半身を自立させておく為に、両手を支柱代わりにしていなければならなかった。身体を起こすと、重かった身体は先程よりもさらに重く感じられ、しつこくまとわりつくような気味の悪い吐き気さえも感じられるようになってしまった。
私が自らの身体に入った鉛によって重い水に沈みかかろうとしていると、部屋の扉が控えめにゆっくりと開かれて、扉の隙間から誰かが顔を覗かせたのに気が付いた。その人物は動けない私の姿を見ると、すぐに表情を明るくさせてその全身を身軽に部屋の中に潜らせてきた。その動きを見て、私は自由に動けないのに、何故彼女はこうも軽々と動けるのか少々不思議でならなかった。彼女は湖の水面を滑る妖精のように私に近づくと、再び私に笑みを見せてから口を開いた。
「もう、お目覚めになったのですか? もう少しお休みになった方が良いのでは?」
彼女の声はホールの反対側から聞こえて来るように、くぐもって反響した音となって私の凝固しかけた脳に届いてきた。私は回転し続ける視界を動かし、声の聞こえてきた方向に何とか視線を向ける。すると、濁って見え難い視界に見慣れた顔が写りこんだ。水の上を滑って来たのは妖精ではなくもっと別のもので、それは例えるならば悪魔か何かが適当なのかもしれなかった。すると、ここは清らかな湖ではなくて、もっと邪悪な水の上に違いない。そして、ここは太陽の光が届かない所なのであろう。個人的には面白い冗談を考えたつもりだったのだけれど、その時に頭痛が一層激しくなったから脳が面白くないと否定しているに違いなかった。自らの脳に否定されるというのも少々憐れなものだった。
「ここは地獄ですよ」とは目の前の人物は言わなかったが、私に対して疑問と哀れみと、心配と好奇の中のいずれかが含まれた視線を向けていたのは事実であった。そのどれかを見極める為には、私の脳は固まりすぎていたし、胃の中に沈んでいる鉛が思考を妨げていた事に間違いはなかった。
とりあえず目の前の人物に何かを言わなければならない。そこで、当たり障りの無い台詞を口から吐き出そうと開きにくい口を開くと、息と一緒に声帯を震わせる動作を私は試みた。身体から空気を出すと、私の身体が水の中に沈んでしまいそうになった。
「ええ、起きたわ」
と、私は声を出したつもりだったのだけど、相手に聞こえたかどうかはわからなかった。だが、とりあえず音は出ていたのだろう。相手は表情を崩さずにゆっくりと頷くと、持っていた銀の盆から明るい青に輝く水差しと薄い硝子で出来たコップを一つ、私の脇に置いてある小柄な机へと移し始めた。
その動作に対して私は視線を向けつつ、水に浮いている記憶を拾い集める事にした。私の浮いている濁った水の上には、これまでの記憶がヘドロか塵のように浮遊していた。もう既に沈んで見えなくなっている記憶も数多くあるようだったけど、私は拾い集めやすい位置に流れ着いた記憶から手を伸ばしてみようと考えた。動かしにくい身体を無理矢理動かしてまで拾う必要は無いだろう。それに、身体を動かしたら水の底に沈んでしまいそうだった。
「昨晩は遅くまで、お嬢様とご一緒でしたね」
私の意識が浮いている水よりも綺麗な澄んだ水の入った水差しを机に置き終わると、彼女は言った。濁った水の底から、記憶が一つ浮かんできた。そう、私はレミリアと一緒に居たのだ。座りなれた心地良い椅子に腰を沈め、満月のように丸い机に乗せられた真っ赤な液体を凝視していたのを覚えている。触れたら割れてしまいそうなコップに水が注がれた。
「お二人で相当数を空けられたようで」
また一つ浮かんだ。そう、途中から何本を空にしたのか分からなくなっていた。でも、何を空にしたのだったか。目の前にコップが差し出される。私はおぼつかない手つきでコップを受け取ると、空気を吸う為に水面で喘ぐ魚のように水に口をつけた。水が身体に入ると、少しだけ浮いているのが楽になったような気がした。ただ、胃に溜まった鉛はしつこく粘りついていて嫌だった。
「こあ、私は何を空けたのかしら?」
言葉が先程よりもスムーズに出てくるのを感じた。ただ、出てきた言葉は非常に間の抜けた言葉だったに違いない。相手は少々困惑した表情をした後に、回転数を落としたレコードのようにゆっくりと音を発した。
「ワインです、パチュリー様」
そうだった。私はレミリアに誘われて、他愛も無い会話をしながらワインを飲んでいたのだった。私の周りに浮かび上がった記憶が着々と流れ着いている。だが、水はいまだに濁ったままだった。濁って淀んでいる水に浮いているせいで、手に持ったコップの清らかで無害な水が実際には存在しない物のように思えて仕方が無かった。
「そうだったわね、思い出した……でも、こんな事になるのは、久しぶりだわ」
私はコップの中の水を再び口に含んだ。口の中が水によって湿り気を帯びる。それが、コップの中には本物の水が入っているという事を私に認識させてくれた。
「では、パチュリー様。私は仕事に戻りますので」
彼女は銀の盆を両手で持ちながら深々と一礼をすると、入ってきた時と同じく水面を滑る妖精のように絨毯の上に軌跡を描きながら部屋から出て行った。彼女の身体が部屋から完全に出てしまうと、扉がわずかばかりの音を立てて閉じた。
「パチュリー様、ご気分はいかがですか?」
その言葉を聞くまで、私は濁った水の中に沈んでいた。水面に引き上げられた私は、慌てて手の中を確認する。コップは消えておらず、先程までと同じようにそこにあった。ふと顔を上げると、濁った景色の向こうに不安げな表情があるのを見て取った。相手の表情が実にはっきりと見えるようになったと言う事は、先程よりは視界が改善されてきているという事だろう。
「ええ、大丈夫。水をありがとう、こあ。まだ気分は悪いけど、大分よくなったわ」
私の言葉を聞くと不安げな表情をしていた小悪魔は、一気に表情を明るくさせた。
「パチュリー様がこんな風になるなんて珍しい事ですから、心配しましたよ?」
「心配をかけてしまってごめんなさい、ワインは美味しいけれど程々にしなきゃいけないわね」
私は固まって動き難くなっていた表情を動かして笑顔を作った。だが、上手く行っただろうか。きっと、引き攣った笑顔になってしまったに違いない。しかし、小悪魔はそんな私にいつも通りの明るい笑顔を返してくれた。
「ワインを飲まれてたのですね。そんなに美味しいワインだったのなら、少し残しておいて欲しかったですよ」
小悪魔が明るい声でおどけてみせた。彼女の明るい声を聞くと自然と自らの顔に笑みが浮かぶのを感じて、未だに具合は悪いが表情だけは先程よりも柔らかくなったのではないかと、私は内心で安堵した。その後、彼女は紅茶を飲むかと私に聞いてから、熱い紅茶を用意をする為に部屋を出て行った。
彼女が扉を閉めた後、私は少しばかり後悔をした。目覚めた時、動けなくなる程に具合が悪くなるなんて間違いなく飲み過ぎなのだ。しかも、飲み過ぎの弊害はそれだけではなかったらしい。ふと、手元に視線を落とすと、そこにはまだ咲夜から水を入れてもらったコップが納まっていた。私は少々複雑な気持ちで、たまっている鉛を溶かすべく胃に水を流し込んだ。
-終-