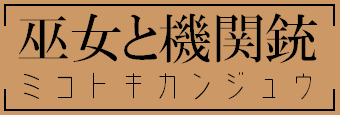短々編09 - 小悪魔の静かな休息
「コーヒーは地獄のように黒く、死のように濃く、恋のように甘くなければならない」
トルコの諺
トルコの諺
図書館の幾重にも連なる書架の間を抜けて、数メートル先も見えない程の薄暗い通路を行くと、その先に煌々と灯りの燈っている場所を見る事が出来る。そこはL字型の分厚い木製の机によって仕切られており、壁に面した場所には大きな背の高い書類棚が設置されていて、中には書類ではち切れそうにならんばかりの帳簿が収められている。その棚にはまだまだ余裕があるようで隙間がちらほらと見えているが、まもなく、そこにも同じような帳簿が収められて隙間は埋まってしまう事だろう。
棚の中に収められた帳簿と同じ物はL字型の机の上にも数冊置かれており、机上に置かれた帳簿の内の一冊は開かれたまま置かれていて、びっしりと書き込まれた小さい文字がランプの明かりに照らされて影のように揺れている。その小さな影は尖った金属製のペン先から滲み出る黒いインクによって紙の上に画かれていて、ペンが紙を擦る音が押し殺した囁き言のように静寂の中から聞こえていた。
やがて、ペンが紙の端まで到達すると、ペン先は宙に浮いて文字を記すのを止めた。その後、ペンは持ち主によって慎重に蓋をされると、机の上に横たわって次の出番が来るまで眠りにつく事になったようであった。ペンの持ち主である彼女は、すらりとした長い指で白いブラウスの袖口に黒いインクが付いていないか丁寧に確認すると、小さな呻き声と共に肺の中の空気を吐き出しながら両手を一杯に広げ、凝り固まった身体をほぐす為に背伸びをした。
彼女が身体を揺らすと、黒いベストの小さなポケットから垂れている懐中時計のチェーンがゆらゆらと振り子のように揺れ、彼女の動きに同調していた。首元に付けられた黒味を帯びた紅いネクタイが鮮やかで、白と黒で構成された服装の中で彼女の真紅の美しい瞳のように映えている。その紅い眼は悪魔にしては少々優しすぎる眼であって、悪魔の持っている威圧感や悪徳といったイメージを感じさせる事は無く、どちらかと言うと温和な印象を与えているようであった。
彼女は片手で真っ赤な髪をなで付けて整えると、自らの脚で地面を蹴って椅子を少し後ろに動かし、机から自らの身体を引き離した。椅子の脚が床に敷かれた紅い絨毯の上に描いた波は消えず、それは彼女が立ち上がってから椅子を押し戻す時まで残っていた。
L字型の机の上はペンや書類、帳簿、スタンプ台などの事務用品で溢れていたが、その片隅にはお湯の入ったポットやお茶を入れる為の道具が置かれた場所が存在していた。椅子から立ち上がった後、彼女はポットの傍らまで行って注ぎ口から湯気が出ているのを確認すると、身を屈めて机の下の戸棚から片手から少しはみ出す位のブリキで出来た缶と、透明なガラスに金属の取っ手が取り付けられたプランジャーポットを取り出して、その二つをポットの脇に置いた。その様子は実に楽しそうで、彼女は顔に微笑を浮かべながら、微かに聞こえる程度の小声で鼻歌を歌いつつ作業を進めていた。
彼女はブラウスの袖を少し引っ張って袖口が作業の邪魔にならないようにすると、爪の先まで手入れの行き届いている綺麗な指でプランジャーポットの蓋をゆっくりと開けた。その際、金属製のプランジャーがガラスに当たり、プランジャーポットが透明な声で小さく短い悲鳴を上げていた。彼女は取り外した蓋を机の上に置くと、何処からとも無くスプーンを取り出し、ブリキ缶の蓋を開けて中へスプーンを差し入れた。ゆっくりと焙煎された後に程よく中粗挽きにされたコーヒー豆が缶の中に入っており、彼女は手馴れた手つきでプランジャーポットの中へとコーヒー豆を移した。そして、余分な香りが逃げないように手早くしっかりとブリキ缶に蓋を閉めた。
彼女は蓋を閉め終えたブリキ缶をスプーンと共に戸棚へ片付けると、湯気を上げているポットを持ち上げてコーヒーの入ったプランジャーポットへお湯を注いだ。ポットから熱いお湯が注がれると、コーヒー豆はプランジャーポットの中で舞い上がり、つむじ風が落ち葉を巻き上げるかのようにお湯の中で踊っていた。お湯を入れた瞬間からコーヒーの香ばしい良い香りは辺り一帯に広がり、それは、図書館の中の陰気なカビ臭い空気が一瞬だけ消えたようにも感じられる程であった。彼女はコーヒーの香りを肺一杯に吸い込むと満足そうな表情を浮かべながら、湯気を上げているプランジャーポットに待ち遠しそうな視線を向けて蓋をした。
コーヒーが十分に抽出されるまでは暫く時間がかかる。彼女はコーヒーが飲み頃になるのを待っている間に、これまでしていた作業で散らばっていた机の上を綺麗に整理をし、くつろいで休憩が出来るように環境を整える事にした。筆記具を引き出しに片付け、整理の終わった帳簿の番号を確認して書類棚の空いている場所に収める。そして、まだ整理の終わっていない帳簿は、閉じて机の端に重ねて置いた。彼女は作業をしている間でも時々、細く湯気を上げているプランジャーポットに眼を向けながら、その時が来るのを今か今かと心待ちにしていた。最後に、彼女はいつも使っている白いカップとソーサーを取り出すとポットの脇に丁重な手つきで置いて、ゆったりと広がる湯気の良い香りを再び吸い込むと口元を綻ばせた。
「やあ、小悪魔。こそこそと何をしているんだ?」
視界の外から現れた突然の訪問者に掛けられた声は平凡な言葉ながらも、無防備になっていた小悪魔の身体を痙攣させるのに十分過ぎるものであった。慌てた小悪魔は机の上のカップを落としそうになりながら、実に聞き覚えのある声が聞こえてきた方へ素早く視線を向けた。そこには、黒い服を身に着けて箒を片手に持った魔法使いが机の端に寄りかかり、実に楽しそうな笑みを浮かべているのであった。
「ま、魔理沙さん……びっくりさせないで下さい……」
小悪魔は引き攣った笑みを浮かべながら魔理沙に言った。そんな小悪魔を見て、魔理沙は押し殺した笑い声を上げた。
「そんなに慌てて、企み事なんて感心しないぜ?」
「企みだなんて……別に、怪しい事なんてしてませんよ……」
「そうかい? なら、後ろに隠してる物を見せてくれても、良いんじゃないか?」
何故か一瞬だけ戸惑った小悪魔だったが、魔理沙の居る位置からポットが見えるように渋々といった風にゆっくりと体を横へ動かすと、自らは悪い事を何もしていないのにも関わらず、なぜか弁解をするような口ぶりで、一休みをしてコーヒーを飲もうと思っていただけ、と言った。
そんな小悪魔を尻目に、すでに良い具合に抽出されかけている真っ黒な液体の入ったプランジャーポットを見て、魔理沙は少々意外だという表情を浮かべた。
「へぇ、コーヒーか。紅魔館には紅茶しかないと思ってたぜ」
「以前、咲夜さんからお裾分けしてもらったのですが、パチュリー様は紅茶派なのでコーヒーは飲まないのです…飲まないのも勿体無いので、私がパチュリー様から頂いたのですよ。あ、魔理沙さんも一緒にいかがですか?」
小悪魔は魔理沙が頷くのを確認すると、戸棚の中から使っていないカップを一つ取り出して机の上に置いた。そして、ガラスのポットを覗き込んでそろそろ頃合だと察すると、プランジャーをゆっくりと押し下げてコーヒー豆を沈殿させた。コーヒー豆がプランジャーによってポットの下に押し下げられたのを確認すると、小悪魔は並べられた二つのカップにコーヒーを注ぎ始めた。
カップに勢い良くコーヒーが注がれると、湯気と共に今までポットに閉じ込められていた香りが空気中に一気に開放されて広がるのが感じられた。ポットの中身を全て注ぎ終えると、小悪魔は二つあるカップの内の一つを魔理沙の近くに置いてそっと静かに差し出した。魔理沙はカップの中の液体にしばらくの間、物珍しそうな好奇の目を向けていた。真っ白なカップに注がれた闇夜のように真っ黒なコーヒーは対照的で、そのツートンカラーが実に美しく感じられた。机の上のカップという小さな世界に、決して混ざる事の無い白と黒が存在している。
「なあ、小悪魔。レミリアがコーヒーを飲むとしたら、やっぱり血を入れるのかな?」
魔理沙からの突然の質問に小悪魔は少し間を置いて考えると、ゆっくりと確認をするように口を開いた。
「さあ…どうでしょうか…レミリアお嬢様も、パチュリー様と同じように紅茶をお飲みになるので、コーヒーは飲まないでしょうが…やはり入れるのではないでしょうか?大量の砂糖と一緒に。」
魔理沙は血液を入れたコーヒーという物を想像して、自らの頭の中で何やら妙な物が首をもたげて来るのを感じた。真っ黒なコーヒーに真紅の鮮やかな血を入れたらどうなるのだろうか。その時、コーヒーは、黒以外の色になりえるのだろうか。黒というのは何色にも染まらない不変の色である筈。それ故に黒は黒でしかない。だが、本当にそうなのだろうか。変化せぬ黒でも、何色かに変化する時があるのではないだろうか。もし、変わる時があるならば、それは一体、どのような時なのだろうか。
「魔理沙さん、どうされました?」
突然、声を掛けられた魔理沙は、はっとして小悪魔へ視線を向けた。視線の先の小悪魔は小首を傾げ、不思議そうな表情を浮かべながら魔理沙をじっと見つめていた。
「あ、いや……なんでもない、大丈夫」
「そうですか、それならば良いのですが…突然、真剣な表情になるのですもの…」
疑いの目で自らを見る小悪魔を見て、魔理沙は耐えられなくなったように笑い飛ばすと、先程までの表情とは一変して明るい表情になった。そして、手元に置かれたカップを一瞥すると、魔理沙はけろりとした口調で小悪魔に言った。
「さあ、コーヒーが冷めない内に飲む事にしようぜ」
小悪魔は魔理沙のあまりの変わり身の早さにただあっけに取られて、驚きとも不審ともつかない妙な感情を抱いていたが、錆付いた絡繰り人形のようにぎこちなく首を縦に振った。そして、二人はカップを手にすると、朔の月が昇る夜のように黒い丸い窓の中を覗き込んだ。
「あ、そうだ。一つお願いがあるんだけど……」
小悪魔は口に運んだカップを傾けかけていた手を止めて魔理沙の方へ注視すると、カップを両手で持ったまま彼女が次の言葉を発するのを待っていた。小悪魔の手に持ったカップから立ち上る湯気が、まるで白いヴェールのように彼女の顔を隠していた。そして、魔理沙は手で上げる事の出来ないヴェール越しに小悪魔に囁きかけた。
「砂糖を、もらえないかな……少しだけ」
-終-