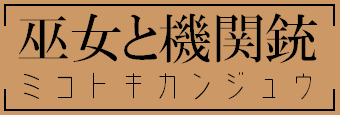短々編10 - 部屋の角
小悪魔の視線は部屋の片隅に釘付けにされていた。
何も無いはずのただの薄暗がりが、妙に濃くなっているように感じたからだった。普段なら気にも留めない部屋の角という空間が、今の小悪魔にとっては気になって仕方が無い場所へと変化していた。それは、部屋の角にある壁と壁の接合部に靄が掛かったようにかすんでいて、何かの気体が溜まっているかのように見えているからなのだった。その光景は胸騒ぎがするほど異常ではあったが、そんな事よりも重要なパチュリーの声によって、小悪魔の注意は部屋の角から逸らされる事になってしまった。
「小悪魔、ちょっと良いかしら?」
「ええ、何なりと……」
「あら……ねえ、どうしたの? 部屋の隅ばかり気にしちゃって」
「申し訳御座いません、何もありません……」
小悪魔はパチュリーに嘘を付いた。しかしこの時、パチュリーが微笑むかのように少しばかり口角を上げたのには、小悪魔は気付いていないようだった。
「あまり、ぼんやりとしていないで頂戴。今日のあなたは少し変だわ、何かあったの?」
「いいえ……何でも無いのです、パチュリー様」
その受け答えから小悪魔は、部屋の角という空間を極力気にしないように、自らの意識に注意を払わなくてはならなくなってしまったのだった。
パチュリーから言いつけられた用事は数分と掛からなかった。目当ての本を書架から取り出し、それを彼女の許へ持って帰れば良いだけの仕事である。だが、小悪魔は仕事をしている最中も、あの部屋の片隅が気になって仕方が無かった。
あれは、何かの事変が起こる前兆に違いない。もしかしたら、パチュリーの身に危険が迫っているのかもしれない。そう考えた小悪魔は、歩む速度を上げると、帰路を急ぐ事にした。
部屋の隅の異変は大きくなっていた。それは確かに、見間違いの無い程に大きくなっていた。
暗がりでうずくまっていた霞が大きくなり、既にランプの光が届く部分までも侵食し始めている。そして、小悪魔は鼻につく何らかの悪臭も感じ始めていた。それは酷い臭いで、呼吸が苦しくなる程であり、まるで腐敗臭のような、一度吸い込むと鼻を覆っても鼻腔にこびり付くような臭いだった。
「パチュリー様、あの……」
「ありがとう、本はそこ辺りに置いて頂戴」
「あの、臭い……変な臭いがしませんか?」
「何を言ってるの? 普段と変わらないわよ?」
パチュリーの返答を聞いて、小悪魔は耳を疑うと同時に、自らの嗅覚も疑い始めた。しかし、確かに悪臭はする。そして、こうしている現在も、部屋の隅の闇は膨らんできている。
「部屋の角……角に、何か……居ます……」
小悪魔は小声で言った。それは、部屋に居る何者かに聞かれるといけないと考えての行動だった。しかし、パチュリーは小悪魔の顔をじっと覗き込んで眉をひそめるだけだった。
「どうしたのよ……あなた、疲れているんじゃない?」
「し、しかしっ……確かに、あそこに……」
パチュリーに対して、部屋の角から迫り来る“モノ”を見せようと、小悪魔は自らの指を先程から何かが漂っている暗闇へと向けた。しかし、小悪魔の指は虚空を指しただけで、パチュリーに対して何の証拠すらも指し示す事は出来なかった。そう、すでに部屋の隅は元通りになっていたのだ。
「あ……れ……?」
「こあ……変な事を言って、私を脅かそうとしているんでしょ?」
「いえ、そんなつもりじゃ……」
「まあ、良いわ……お茶を用意して頂戴」
いまいち納得の出来ない小悪魔は、問題の場所へ視線を残したままパチュリーへ返事をした。しかし、どんなに部屋の角が気になろうとも、自らの意志よりも効力のあるパチュリーの指示に従って、紅茶を用意する為に部屋の外へ向かわなくてはならないのだった。
「はい、分かりました……パチュリー様」
あの闇は何だったのか。淀んでいた黒いモノは何だったのか。小悪魔には全く理解できなかった。だが、小悪魔にとって理解する必要の無い事なのだ。
それは、小悪魔がこれからもパチュリーの傍に居たいと考えていれば、尚更の事なのである。
「もう、あの子が居る時に出てきちゃダメじゃない……」
小悪魔の背後から、聞きなれたパチュリーの声と共に何かの唸り声が聞こえていた。
-終-