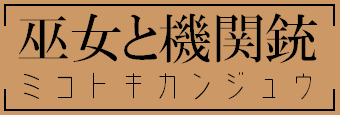短々編11 - 慕えぬ慕情
そよ風によって流されてゆく白いレースのカーテンのように、無数に文字の印刷された紙がめくられて行く。それは、春の希望に満ちた光景のようでもあり、秋の物寂しい情緒溢れる光景のようにも思われた。
私は目の前の本に描かれた文字が教えてくれる知識を、必死に意識して記憶に留めようと努力をしていた。いつもならば、そんな努力など必要無い。でも、今は文字を読もうと思わないと、本と眼の間に壁が出来ているかのように、文字が読めなくなってしまう。
私は、手を伸ばせば届いてしまいそうな場所に存在しているものへ、意識や視線を向けないようにしている。それでも、私はそちらばかり気になってしまい、視線はその方向にしか向けられないようになってしまっているらしい。私が避けているそのものは、普段と変わらぬ服と変わらぬ仕草を身に付けながら、書架の前で忙しなく仕事をしているだけのこあに違いないのだけれど。
いつも通りのこあのはずなのに、私の視線は彼女の背中に固定されてしまったかのようで、何故か眼を逸らす事が出来ない。そして、彼女の腕の一挙動や溜息一つまでも鮮明に見えてしまう。不思議な事に、彼女の真紅の髪が揺れる度に私の気持ちも揺れ動くようで、先程から湖に浮かべた小舟に乗っているような錯覚さえも覚えているようだった。
その小舟の上では私は無力で、舟をこぐ為のオールさえ見当たらない。私の乗る舟は風任せに漂っていて、湖の沖へ漂うのも岸へ流れ着くのも彼女という風が全てであるかのようだった。湖の岸は深い霧によって見る事が叶わず、私一人ではどうする事も出来ない。しかし、そんな状況でも私は助けを求めて叫ぶつもりは無かった。それは、私以外の誰かに、私の心中を知られたくないからに他ならない。
それでも、それはただの強がりでしかないらしい。私の頬は既に熱を出した時のように熱くなっていて、鏡など無くても真っ赤である事が手に取るように分かった。だけど、私はそれを認めたくはなかった。頬の熱さを感じれば、胸騒ぎをより強く感じる事になる。ただでさえ胸が張り裂けそうなくらいに切ないのに、今以上に苦しくなると、私の胸は耐え切れなくなって破裂してしまうだろう。
今、私の胸は病に掛かってしまいそうな程に痛かった。このままでは、その存在が懐疑的だったとある患いを、自らの身体をもって証明してしまう事になりかねない。だから、私は無理矢理にでも彼女を自らの意識の外へ追い出さなくてはならない。そこで、目の前にある本へと出来る限り意識を向けて、今現在の感情を押し殺す事を自らに強要している。私はこあの、彼女の主人であり続けなくてはならないのだと自らに言い聞かせながら、主人としての威厳を保つ為に、彼女に対する感情を殺している。殺し続けている。
しかし、幾重にも重ねた感情の屍骸の中からは、感情そのものが燃え上がるように顔を出してくるのだ。これまで私は、顔を出し始めた感情の上へ再び屍骸を乗せる事で、その顔を見ないようにしてきた。だが、その行為自体はただの遅延行為にしかならず、問題を根本から解決する事なんて出来る訳が無い。
それが分かっていたからこそ、私は別の言い訳を考えなくてはならない潮時だと痛いほど感じていた。そこで、こう思う事にした。こあは悪魔である。その為、夢魔のように人を惹きつける事が出来るに違いない。ましてや、他人の心を操作してしまう事など容易に出来てしまうに違いない。私は、彼女の魔術にしてやられているのだと。そう考える事によって、少しは胸が楽になるような気がした。
しかし、すぐに別の問題が噴出する事になる。新しい言い訳を理解し、そう思い込んだ次の瞬間には、これ以上辛い思いをし続けるならば、彼女の作り出す毒ガスのように漂う罠に飛び込んで、自らの胸一杯に彼女の毒を吸い込んでも良いと思い始めていたのだった。
いかに耐えるのが辛くとも、彼女の毒に掛かって頓死するのは簡単なのである。ただ、眼を閉じて彼女の名前を呼ぶだけで良い。それで全ては終わる筈で、この苦しい切なさすらも霧散してしまうに違いない。ああ、なんと楽な事だろうか……無理に舟の縁にしがみ付く必要は無い。湖の波に身を任せ、先の見えない霧の中へ消えてしまえば良いだけの事。
でも、それを実行に移す勇気など私には無かった。結局のところ私には、揺れる舟の縁に必死にしがみつきながら深い水の中を覗き込み、決して見える事の無い湖底へ慕情を募らせる事しか出来ないのだから。
いつかこあが、私をどこか遠くの幻影と夢想にまみれた世界へと連れて行ってくれる。そんな来るはずも無い日を空想の中へ描き出しながら、私は身の入らぬ本へと意識を向ける。勇気のない自らを呪い、愛しいはずの彼女を恨み、それでも現状を変えてはならないという蜘蛛の糸のように絡み付く使命感に自らを覆いながら。
それでも、私の視線はこあへ向けられていた。黙々と作業を続ける彼女の後姿へと。自らで抑圧している気持ちが届いて欲しいと願いながら、私は必死に感情を押し殺し続けているのだった。
-終-