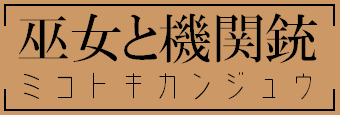短々編12 - 薬の微々たる副作用
私はじっと黙ったまま、目の前でゆっくりと昇ってゆく白銀色の水銀の線を見つめていた。その線は私を焦らそうとしているかのように、緩慢な動きでガラス管の目盛を辿って行く。しばらくすると、水銀はこれ以上は昇れぬ所まで到達したらしく、私が目盛を読むのを待ってくれているようだ。
「37度9分。少し下がったけれど、まだ熱があるわね」
私は小さく呟いた。すると、ガラス管がゆっくりと振り子のように左右に揺れ動いて言葉に反応した。しかし、私の言葉に反応を示したのはガラス管ではなく、その管を口に加えながらベッドに横たわっている彼女が頷いたのだった。
「大丈夫よ。ご飯も食べたし、薬も飲んだんだから、すぐに良くなるわ」
私は目の前のベッドに横たわる彼女、メリーにゆっくりとした口調で語りかけた。
彼女は数日前に熱を出して寝込んでしまったのだった。病院の医師はただの風邪だから心配は要らないと言っていたけれど、私は心配で彼女の脇につきっきりで看病をしている。寝込んだばかりの時、彼女は高熱でうなされていたり、酷い頭痛や吐き気と戦っていたが、今朝になってようやく軽い食事を取れるまでに回復をしたのだった。
潤んでぼんやりとしている瞳でこちらを見つめる彼女を少しでも勇気付けようと、私は彼女の頭に手を触れて優しく撫でる。そんな私に対して、彼女は熱で紅潮した頬を緩ませて微笑み返してくれた。それはぎこちない笑みではあったが、私を安心させるには十分過ぎる程のもので、そんな彼女を見つめながら私は胸を撫で下ろしたのだった。
「そうね……念のため、解熱剤、使いましょうか」
私は彼女の口から体温計を抜きながら言った。抜き取った体温計は彼女の唾液で少しばかり湿っているのが分かる。私は、手近にあった清潔なタオルで体温計を拭き取ると、ベッドの脇に置いてある小振りのテーブルに乗せた。
「解熱剤……使うの?」
私の発言を受けて、彼女は少々困惑したような表情を浮かべた。そして気のせいか、少しばかり顔が先程よりも赤らんでいるようだ。彼女に現れた変化を不安に思いつつも、テーブルの上に置いてある医師から処方された薬の入った袋を手に取りながら私は言った。
「ええ、使っておきましょうよ。まだ熱も高いし」
「ちょ、ちょっと待って蓮子……あのね……」
私が袋を開こうとすると、彼女はいやに慌てるのだ。それは、異常と言って良いかもしれない様相であった。
「どうしたのよ、メリー? お医者さんから貰った薬を使うだけでしょ、何を慌てているのよ?」
「いえ、その……解熱剤は、使わなくていいわよ……ね?」
明らかに彼女は、私が薬を使おうとしているのを阻止したいようだ。しかし、私にはその理由が良く分からないのであった。なぜ、彼女はここまで必死になっているのか。私はその理由について考えながらも、手を動かして袋の中から薬を取り出そうとしていた。
彼女は解熱剤を使う事を何故そこまで嫌がるのか。結局、私は思い当たらないままに、解熱剤を袋から取り出してしまった。その瞬間、彼女は口をモゴモゴさせながら、私から視線を逸らしていた。
「まだ、具合は良くない? 頭痛がする?」
「……いいえ、違うの」
「じゃあ、吐き気がするのかしら?」
「いいえ、違うわ」
「エ……それじゃあ、一体……どうしたのよ?」
私の問いに対して、彼女は身体に掛けられた厚い布団の中からゆっくりと腕を出して、ぴんと伸ばした指で私の手を差した。
「それ、その薬……嫌だわ」
彼女に言われ、私は手元に視線を落とした。私の手には先程から解熱剤が乗っていた。それは、パックに入った丸みを帯びた細長い薬剤で、一見すると弾丸のようでもあった。ただ、命を奪う弾丸と違うのは、これは薬であって人を辛い病気の症状から救う為の物であるという点だろう。
それにも関わらず、彼女はまるで猟銃を向けられているかのように脅えているようである。私はそんな彼女の誤解を解いてあげる為に、優しい口調で諭してやろうとしたのだった。
「大丈夫よメリー、何も怖くなんてないわ。だって、熱がすごかった時に一度使ったのよ」
どうやら、私の発したその言葉は彼女にとって逆効果だったようだ。彼女は突然の発砲に驚いた小動物ように眼を見開いて私を見つめたと思ったら、耳を真っ赤にしながら勢い良く頭まで布団に潜ったまま出てこなくなってしまった。
途方に暮れた私は無用になった解熱剤を手にしたまま、どうする事も出来ずにいるのだった。そして、こんな結末に至ってしまった今でも、どうして彼女がこの薬、坐薬を嫌がっていたのか理解する事が出来ないのだった。
-終-