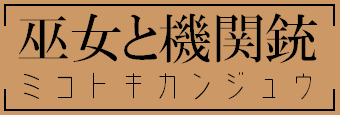短々編02 - 日陰の少女は振り向かない
私が何をしようとも、彼女の視線は決して私を捉える事が無かった。私は彼女に振り向いて欲しかったのだ。私の目を見て微笑んで欲しかった。だが、彼女は目の前に広げた本しか見ていない。彼女は、私がいかに焦れったい気持ちになっているかなど分かっていないだろう。彼女の目には紙に書かれた文字しか写っていないのだから。そんな風に時間が虚しく過ぎていくのに耐えられなくなった私は、遂に席を立つ事にした。
あっちにある本棚を見てくる、と私が声を掛けても彼女は、微かに首を縦に振っただけであった。こちらを向く事も無く、声を出す事も無い。私は続けて声を掛ける事も出来ず、彼女と話す口実を作る為に放った言葉に従わざるを得なくなってしまった。だが、彼女から離れる度に、まるで彼女の心までも遠ざかっていくようで、あまり遠くの書架には行きたくなかった。そこで、程々の所で曲がると読みたくも無い本を物色し、読みたくも無い本を数冊取り出してから、彼女の元へ戻る事にした。
彼女の元へ戻ると、先程と同じ姿勢で彼女は本をじっと読んでいた。私は、それにがっかりすると同時に、何故か大きな安心感を感じている自分が居る事に気がついた。私は持って来た本を机の上に落とすように置き、わざと大きな音を立ててみた。そして、彼女に聞こえるような大きな声で収獲を報告してみたりした。だが、彼女は振り向いてくれない。空しかった。自分のやっている事が空しかった。声を掛けようが何をしようが、彼女は振り向いてくれない。ましてや、彼女の声なんて暫く聞いてない。彼女の口が開くのは紅茶を飲む時と、欠伸をする時位だった。私は彼女の声が聞きたかった。彼女と会話をしたかった。けれど、それも難しい話である。私は何ともいえない空しさを感じていた。心の底から湧いてくる空しさ。まるで胸の真ん中が空洞になってしまったかのような。この感覚は、もう何度も味わっている。しかし、何度味わっても慣れる事なんて無い。喪失感。虚無感。自己嫌悪。 それらが何重にも重なって、この空しさを作り上げているのだ。こんな気持ちになってしまったら、もう、それ以上は何も出来ない事は私にも分かっていた。だから、早々に引き上げなくてはいけない。彼女の前で弱い所は見せたくないのだ。彼女の前では暗い素振りを見せたくないのだ、絶対に。
図書館から出て、館の玄関先に立つとひんやりとした風が私の身体を流れていくのを感じた。もしかしたら、彼女にとって私はただの風に過ぎないのかもしれないのだ。彼女の持っている本を必死に取り上げようとしている空しい風。だが、弱々しい風は何もする事が出来ない。彼女は私を何とも思っていない。ただ、自らの生活圏に入り、本を持っていくだけの存在。そう考えていると、自らの胸の空洞が更に広がるような気がして辛かった。
「あら、今日も本を持っていくのですね?」
館の立派な門から出ようとすると、門の脇に立っていた一人の門番が突然、声を掛けてきた。
「うん、いっぱい持ってきたぜ。」
私は精一杯の明るい笑顔で門番の問い掛けに答えた。顔に貼り付けた笑顔が虚しかった。
「そうですか…でも、借りたらちゃんと返してあげてくださいよ。」
門番も顔に笑みを浮かべていた。私のような笑顔じゃなくて、本物の笑顔だ。
「そうだな…もし、取りに来たら考えてやっても良いかもだな。」
と、私は門番に言ったが、これは門番に言うべき事では無いのは明らかであった。これは彼女に言うべき言葉だ。だけれど、彼女に言える訳が無い。言った所で、彼女が何か反応を示してくれるのだろうか?
私は門番と当たり障りの無い挨拶を交わして館を後にしたが、あと何回こうやって彼女の許を訪れれば、彼女は私を見てくれるのだろうか。あと何冊持っていけば、私に言葉を掛けてくれるのだろうか。私には分からなかった。私が本で埋まってしまう前に、声を掛けてくれれば良いのだけれど。
-終-