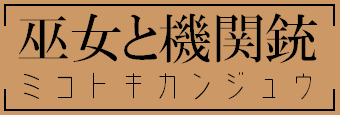短々編04 - 朝焼けは珈琲の香りと共に
薄っすらと照明の灯された薄暗い寝室は、とても居心地の良い場所であった。落ち着いた装飾の施された室内には上質な絨毯が敷かれており、壁には見るからに高価そうな絵画が掛けられていた。部屋の中央には大きな天蓋付きの寝台が置かれており、その寝台の上には少女が一人、静かな寝息を立てて眠っている。そして、その寝台の脇の椅子には、まるで眠っているかのように一人のメイドが静かに座っていた。紅魔館のメイド長である咲夜は館の主である少女が寝付いた事を確認すると、ポケットから銀の鎖の付いた懐中時計を取り出して時刻を確認した。時計の針は、そろそろ日の昇る時刻である事を教えてくれた。部屋の外では、妖精メイド達が窓にカーテンを引く音が微かに聞こえて来ている。彼女は、椅子から立ち上がると滑るように絨毯の上を歩いてゆき、音も無く扉を閉め部屋を後にした。
紅い絨毯の敷かれた廊下は、微かな蝋燭の明かりで照らされているだけで薄暗かった。光を取り入れる為の窓には分厚いカーテンが掛けられており、外から入る光を完全に防いでいた。この館に住む者にとって、光は必要の無い物だ。いや、必要無いのではない、むしろ邪魔なのである。
これから朝を迎えようとしているのに、館の中は全てが寝静まってしまっているかのように静かであった。そんな静かな廊下には彼女の足音だけが聞こえ、壁にぶつかった音は小さな反響音を残して暗闇へと消えていった。足音を聞きながら歩いていると、自らの足音の他に廊下の奥の方から足音に呼応するように別の足音が聞こえてきた事に気付いた。足音は次第に大きくなっていくと同時に、向こうから歩いてくる人物の輪郭がぼんやりと見え始めた。その輪郭は徐々にはっきりと見えるようになって行き、最終的にはそれが小悪魔であると認識できるまでになった。小悪魔は手にティーポットとカップを乗せた銀の盆を持っており、ポットからは温かそうな湯気が立ち上っていた。
小悪魔は疲れきった顔をしており、本人は気付いていないだろうが、体から薬品の妙な臭いを発していた。どうやら、徹夜の実験に付き合わされていたらしい。すれ違う際、小悪魔は微笑みながら軽く頭を下げたのだが、小悪魔はやつれていて眼の下に隈すら浮かんでいた。
小悪魔とすれ違った後、彼女はどこまでも続く長い長い館の廊下を歩き続けて、一枚の扉へと辿り着いた。そして、木製の扉を開くと、その先は館の厨房になっていた。彼女は手馴れた手つきでポットを火に掛けると、戸棚から良い香りのするコーヒー豆を取り出して用意をした。その無駄の無い手付きは、見ていてとても気持ちの良い物であった。ポットが勢い良く湯気を噴いてお湯が沸いたのを知らせると、彼女は火を止めて用意していたフィルターにゆっくりとお湯を注いだ。紙製のフィルターにはコーヒー豆がいっぱいに入れられていて、お湯が注がれると一斉に良い香りを辺りに振りまいた。彼女は少しだけお湯を入れて豆を濡らすと、お湯の温度でコーヒー豆を蒸らした。待っている間、コーヒーの香ばしい良い香りが厨房中へ広がっていった。十分に豆を蒸らした後、彼女はお湯をいっぱい注いでコーヒーを淹れると、出来立てのコーヒーを保温ポットに注ぎ、それをマグカップと一緒にバスケットへそっと入れた。そして、使った道具を片付けるとバスケットを持って厨房を後にした。
厨房から出た彼女は真っ直ぐ玄関へと向かうと、重い扉を開けて外へ出た。遠くの方では太陽が半分ほど顔を出していたが、空気は肌寒かった。彼女は室内との温度差に身震いをすると、館の前庭を歩み始めた。辺りを見渡すと、軽く霧が掛かっており視界がぼんやりと霞んでいた。振り返ると、今出てきたばかりの巨大な館が少し霞んで見えた。真っ赤な壁が少々白くなって、何やら淡い色になりかかっていた。館の何処かにある窓のカーテンが少し揺れたような気がしたが、波を打っていたカーテンはすぐに動かなくなった。彼女は館から視線を逸らすと、再び歩み始めた。
どの位歩いたか分からなくなり始める頃に、ようやく館の門へとたどり着いた。彼女は門の陰から外を覗き込み、門番がしっかりと仕事をしているか確認して微笑んだ。美鈴はしっかりと仕事を果たしていた。冷たい石の壁の前で寒そうに手を擦りながら、じっと門の前に立っている。彼女は門の陰から出ると、美鈴に声を掛けた。その声を聞くと美鈴は、微笑みながら振り向いた。
「おはようございます、咲夜さん。」
「おはよう、美鈴。今日は冷えるわね。」
「ええ、今日は特に寒いです…手先が凍ってしまいそうですよ。」
美鈴は苦笑しながら手を脇の下に入れて温めた。彼女は思った、美鈴の着ている服では、到底寒さは防げないだろう、と。
「今日は温かいコーヒーを淹れてきたわ。きっと寒がっているだろうと思って。」
彼女は門の脇の霧で冷たくなったブロックに腰を掛けると、バスケットを膝に乗せて蓋を開けた。バスケットの中は保温ポットの温度で少々温かくなっていた。彼女はマグカップを一つ取り出すと、保温ポットからコーヒーを勢い良く注いだ。底の見えない程に黒くて重そうなコーヒーが湯気を立ててカップへ注がれてゆく。それと同時にコーヒーの心地よい香りが辺りに広がって行く。彼女がコーヒーを注いでいる間に、美鈴も彼女の隣へ座ると、カップから立ち上る湯気を見つめていた。カップの中がコーヒーによって満たされると、カップは彼女にとっては熱いくらいの温度になった。彼女はたっぷりとコーヒーの入ったカップを美鈴へ手渡すと、保温ポットを再びバスケットの中へしまい込んだ。
美鈴は暫くの間、カップへ注がれたコーヒーの温度で手を温めていたが、おもむろにカップを口へ持ってゆくと熱いコーヒーを一口すすり、大きく安堵の溜息をはいた。
「寒い時って、温かい飲み物を飲むとほっとしますね。」
彼女に対し、屈託の無い笑みを浮かべながら美鈴は言った。その笑顔を見た彼女は、コーヒーを飲んでいないのに自身の頬が次第に温かくなって行くのを感じた。そんな彼女の脇で、美鈴は美味しそうにカップの中身を飲み続けている。そして、喜んでいる美鈴を見ていると、自分も幸せを感じているという事に彼女は気付いた。だが、何故だろうか。彼女にとって、美鈴はただ単に同じ所で働く同僚に過ぎなかったはずだ。いや、色々手間のかかる大変な存在なのである。仕事中に居眠りをするし、外部の者をすぐに通してしまったりする。しかし、そんな美鈴でも、時には頼りになる存在である事には間違いは無かったし、何よりも美鈴の明るい笑顔や立ち振る舞いが彼女は好きであった。だが、彼女には分からなかった。それでも何故か、急に恥ずかしくなって来てしまって、彼女は急いで視線を逸らした。
「咲夜さん、どうしました?」
美鈴に問い掛けられ、うろたえながらも咄嗟に笑顔を作ると彼女は美鈴に返事をすべく口を開いた。特に何も無い、と彼女は言った。美鈴はその言葉を疑う事も無く飲み込むと、そうですか、と微笑みながら言った。
それから暫く続いた沈黙の間、彼女は空を見上げると、太陽は完全に顔を出して暖かな光を振りまいていた。霧は既に消えかかっていたが、未だに空気は冷たいままであった。気付けば無意識の内に、彼女はすっかり冷たくなった手に自らの息を吹きかけて温めていた。ふと美鈴の方をみると、美鈴は何も言わずに少しずつコーヒーをすすっている。美鈴が息をする度にカップの中のコーヒーが勢いよく湯気をはいていた。彼女は美鈴の座っている方へ気持ちばかり身体をずらすと、控えめにカップの中を覗き込んでみた。美鈴の手の中では、温かいコーヒーが未だに踊っていた。
「美鈴、ちょっと…コーヒーをもらっても良いかしら?」
彼女は小さな声で控えめに言った。美鈴は彼女の小さな望みを快く聞き入れると、カップを彼女に手渡した。手に取ったカップは温かくて、寒さで固まっていた身体が溶けていく様な気がした。良い香りのコーヒーを静かにすすると、立ち上る湯気が彼方の湖の上に消えて行くのが見えた。コーヒーを口に含んだせいか、頬の熱さが中々取れなかった。
-終-