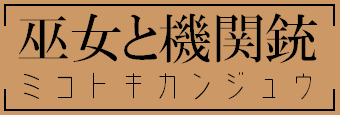短々編05 - 眼を閉じた世界は美しかった
※このSSには、多少なり残酷描写が含まれております※
※閲覧の際はご注意をお願いいたします※
地獄の底まで太陽の光は届かず、地獄の底まで地上の爽やかな空気は流れてこない。そこにあるのは、むせ返るような腐臭と身体にまとわりつく嫌らしい湿り気だけだった。微かな光がステンドグラスから入り込み、冷たい石の床に歪んだ模様を映し出している広間には、物憂げな表情をした少女が独り床に座り込んでいた。彼女は動こうとする気配も無く、ただ真っ暗闇しかないどこか遠くを見詰めていた。しばらく眠っていないのだろうか、眼の下には濃い隈が浮かんで不健康そうな色白な肌をより不健康に見せていた。彼女は時折、はっと気付いたように眼を見開いて視線を左右へ揺らしていたが、すぐにそれも止めて再び虚空を見詰めるという行動を繰り返していた。傍から見れば至極異様な行動ではあるが、それは彼女がどのような状況に置かれているか理解していないからであるのだ。どこかから聞こえる誰かの声が、自らを責め立て罵るのが彼女には聞こえていた。そして、彼女にはその声が、どこか聞き覚えのある声に感じられて仕方が無かった。
その声が聞こえ始めたのはいつの事だっただろうか。いや、彼女にとってそのような声が聞こえると言うのは日常的な事であったのだから、最初は全くもって気になどしていなかったのだ。彼女には他人の心の声が読めるという力があった。だからこそ、初めの内はその力の誤作動、または過剰に反応しているだけなのかもしれないと彼女は思っていた。だが、それは違うと彼女は気付いた。
気が付くと、彼女は共に住んでいる仲間に強く当たるようになってしまっていた。ふと正気に戻ると自分が考えても居ないのに、罵詈雑言を共に暮らす仲間にぶつけている事もしばしばあった。そんな彼女を仲間は心配しつつも忌避し、自然と遠のいていってしまった。自らが招いた事と言え、彼女にはそれがたまらなく辛かった。だけど、それは自らのせいであるという事も痛いほど理解していた。だから、彼女は自らを狭い部屋に閉じ込める事にしたのだ。暗い部屋に独りになる事で、自らを戒めようとした。共に暮らしている仲間を傷つけまいとした。そして、それが最良の判断だと考えていた。自分が再び正気に戻れるまで、彼女は耐え忍ぶつもりだった。その決断のお陰なのか、しばらく聞こえていた声もしばらくすると全く聞こえなくなり、彼女は心に平穏を取り戻す事が出来た。そして、彼女は安堵した。 だが、それはただの思い込みであった。いや、もしかしたら今まで通り聴こえていたのかもしれない。それを彼女は、ただ聴こえないふりをしていただけなのかもしれない。突然、今まで聞こえなかった声が再び聞こえるようになった。彼女はその時、背筋が凍るように戦慄を覚えたのであった。そして、彼女はどうして良いのか分からなくなり、地面に座り込む事しか出来なかった。それから彼女は眠れなくなった。それから彼女は喋れなくなった。自分が動くと、誰かが不幸になる気がしてたまらなかった。だから、共に暮らす仲間にも助けを求められなかった。彼女は独りで悩むしかなかった。そして、独りでこの事を解決するしかなかった。
とある時、彼女は思った。もしかしたら、この耳さえ無ければ今まで聴こえていた声は聴こえないのかもしれないと。そこで、彼女は耳を塞いだ。彼女の世界から音が消えた。何も聴こえず、世界は無声映画のように違和感のある光景になった。だが、あの声だけは聴こえていた。それはまるで、活動弁士の話す台詞のように聴こえていた。彼女は分かっていた。耳を塞ぐだけでは、あの声は消えないと。本当は、彼女の持っている力を塞がなければいけないのだと。でも、それだけは出来なかった。それをやってしまったら、彼女は彼女で無くなる気がしていたから。共に暮らす仲間に見捨てられてしまう気がしたから。
次に、彼女は眼を閉じた。眼を閉じれば何も見えなくなる。見えなければ、きっと声も収まってくれるに違いないと。今まで見えていた無声映画が消えて、彼女の世界からは光が無くなった。だけれど、あの声は消えなかった。そんなのは分かっていた。眼を閉じた位で声が消える訳が無いと。でも、彼女にはどうする事も出来なかった。眼を閉じる以外に彼女には何も方法を思いつく事が出来なかったのだ。もう一つの眼を閉じるなんて、彼女には出来なかったのだから。もし、第三の眼を閉じてしまったら、彼女は皆の気持ちを理解する事が出来なくなってしまうに違いないと考えていた。そんなのは嫌だった。だって、それをしてしまったら、自分は皆から見捨てられるに違いないと考えていたから。
それでも真っ暗で何も聴こえない彼女の世界に、あの声だけが響いていた。嫌だった。嫌な声だった。本当に、嫌な声。嫌で仕方が無い。嫌なんだ。あの声が、まだ、聞こえているんだ。彼女の世界には、あの声が鳴り止まずに響き続けていた。そして、彼女は思いついた。そうだ、自分が話すのをやめれば良いのだ、と。
そして、彼女は口をつぐんだ。彼女の世界からは自分の声が消えた。音が、光が、そして自分も消えた。これで、あの声は聴こえなくなるはず。彼女は、どこかで安堵感を覚えていた。
そして声は、すっかり消えた。
声が消えて彼女は、聞き覚えのある優しい声が聞こえて来るのに気付いた。
それは、彼女が共に暮らす優しい仲間の声。その向こうに仲間の笑顔が見える。
皆が口々に彼女の名を呼びかけている。皆が暖かく迎えてくれる。
彼女は、閉じた眼から涙を流した。彼女は、つぐんだ口から叫びを漏らした。
彼女は救われた。これで、狭い部屋に閉じこもる必要も無くなった。
でも、そんなもの出来る訳が無いのだ。そんなことを感じられる訳が無いのだ。
彼女の眼は潰れてる。だって、自ら潰したのだもの。
彼女の口は開けない。だって、自ら縫い付けたのだもの。
そして、彼女は音を聞く事が出来ない。だって、自ら耳を切り落としたのだから。
それが、彼女が自らに行った償いの行為。自らへの戒め。
彼女はそう思っている。それが償いになると。
だけど、それは本当に、償いになっているのか。
彼女は、自分の世界に閉じこもっていただけだったのじゃないか。
そして、世界は真っ暗になった。
………
………………
………………………
以前の姿からは想像も出来ないくらいに衰弱した姉の姿を見て、こいしは呟いた。
「独りで悩むから、そういう事になるのよ。分かった?お姉ちゃん。」
こいしは姉の傍に近寄ると、すっと跪いて彼女の顎を持ち上げた。彼女が自ら潰した眼からは、真っ赤な血の涙が流れていて痛々しかった。しかし、こいしはそんな姉の姿を見ても無感動であるようだった。むしろ、そんな姉を愛しくさえ思っていた。
「お姉ちゃん、これからも仲良く一緒に暮らしましょうね。」
何も聴こえず、何も見えない姉の潰れた眼窩を覗き込みながらこいしは言った。そして、姉の赤い涙を自らの舌で舐めとると、顔一杯に笑みを浮かべた。
「さあ、お部屋へ戻りましょう。ここは暗くて寒いわ。」
こいしは姉の腕を掴むとゆっくりと引きずるように何処かへ連れて行った。彼女の引きずられた後には、点々と赤い滴りが続いていた。この後、何が起こるか彼女には分からなかった。だがそれでも、彼女は大きな安堵感を感じていた。だって、自らを救ってくれる誰かが近くに居るのだから。
「あはっ、お姉ちゃん…もう絶対に離さないわ…お姉ちゃんが何と言おうとも、私はお姉ちゃんを離さない…大好きよ、お姉ちゃん…」
姉がどう思っているのか、そんな事などこいしには関係無かった。彼女はただ、姉を手放したくないだけだった。こいしは顔一杯に笑みを…だが、先程とは違う歪んだ笑みを浮かべると、暗い部屋の扉を静かに閉めた。
-終-