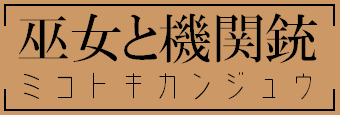日陰の魔女、或いは日向の門番 - 第一回
幻想郷にも春がやってきた。今まで山や丘に降り積もっていた雪も溶け始め、空には暖かい太陽が徐々に顔を覗かせるようになっていた。それは紅魔館の周辺も例外ではなく、積っていた雪も門の脇に薄っすらと残っているだけになった。このような暖かい日ならば、冬の間にお世話になった分厚いコートはもういらないなと門番である美鈴はうとうとしつつ考えていた。美鈴は防寒用コートのボタンを開けて着ており、開いた部分からは普段から着ている濃緑色の服が覗いていた。このような暖かい日差しをいっぱいに浴びて心地よくならない人がいるだろうか、そう考えた後に自らが妖怪である事に気付いた美鈴は苦笑した。こんな気持ちの良い日は人間であれ妖怪であれ、関係なく心地よく感じるだろう。そして、そんな日は暖かい縁側で昼寝をするに限る。自らの考えをそのように結論付けた美鈴は、早くも舟を漕ぎ始めていた。
「あら、門番が寝ているなんて、この館の警備は素晴らしいわね。」
ふと聞こえてきた皮肉の混じった聞き馴染んだ声が美鈴の舟を沈ませた。恐る恐る眼を開けると、そこには美鈴の予想通り、館のメイド長である咲夜が仁王立ちで威嚇していた。咲夜の背後からは言い知れぬ威圧感が漂っており、決して表情には出さないが苛立っている事は明らかであった。
「あっ、いや…これは寝ていたのではなくて…そう、瞬きをしていたのですよ。」
自分でも冷汗が背中をつたうのを感じつつ、必死に言い訳をする美鈴。もちろん、そんな言い訳が通るほど咲夜が間抜けではない事は分かっている。
「そう、それにしてはいやに長い瞬きだったわね。大丈夫?眼にゴミでも入ったかしら?」
咲夜は笑顔だが、その表情の裏には暖かい陽気が吹き飛ぶほどの冷たい感情があるのが咲夜から発せられる言葉から感じられた。これはもう、言い訳などしている場合じゃない。最悪の場合はナイフが美鈴の頭を貫くであろう。それもまた、いつもの光景ではあるのだが。
「いえっ、大丈夫…です。もう、大丈夫ですから…」
美鈴は必死に笑顔で返答したつもりだが、その笑顔が引きつっているのは自分でもわかる程だった。その顔を見て、咲夜は意地悪な笑みを浮かべると踵を返して館に引き返しかけた。それを見てほっと息をつく美鈴であったが、咲夜が足を止めるのを確認すると再び緊張した表情になった。
「美鈴、こうやって一々確認しに来る私の身にもなってよね。私は館の仕事で忙しいのだから。そうだ、そんなに暇ならば…あなた、本でも読んでいたら良いんじゃない?あなた自身の教養にもなるし、あなたが居眠りをしなくなるのならば私も万々歳よ。」
わかったと必死に頷いている美鈴を見るとくすりと咲夜は微笑し、寝ては駄目だともう一度念を押して館の中へ戻っていった。やっと緊張から開放された美鈴は全身の力が抜けていくのを感じて、力なく塀にもたれ掛かった。そして、暖かい太陽の出ている空を見上げると、咲夜の出した案は案外良いかもしれないと考えたのだった。
その夜、仕事が一段落してから美鈴は館の地下にある大図書館へと向かった。図書館へと向かう階段には赤い絨毯が引かれており、壁にかかった角灯が足元を明るく照らしていた。美鈴が図書館へ行くのは、そう頻繁にある事ではない。咲夜から使いを頼まれた時や、図書館の主であるパチュリーから直々に呼び出された時くらいである。とは言うものの前者が大半であり、後者は片手で数える位しかない。階段も終わりかけて最後の一段を掛け声と共に勢い良く降りると、美鈴は図書館への入口である大きな両開きの重い扉を開いた。
扉の先には館の地下にある事を忘れてしまう程の広い空間が広がっていた。その空間には空を埋め尽くすのではないかと思われるほどの高さのある書架が両脇に広がっており、その書架には隙間無く様々な大きさの様々な色をした本が納められていた。そんな書架の間を歩いていると、まるで森の中を歩いているかのような錯覚を覚えてしまう。ただ、普通の森と違う点はこの森はただの木ではなく、膨大な量の知識と情報を詰め込んだ本で構成されているという点であった。そして、その森の真ん中に置かれた分厚く頑丈な木で出来た机で、机の木よりも分厚く頑丈そうな本を広げて読んでいる人物こそ、この図書館の主であり頭脳であるパチュリーであった。彼女は、この薄暗く埃っぽい図書館で一日中―いや、一年中かもしれない―本を読んでいる。そんなに知識を詰め込んでいたら、自分の頭は一週間と立たないうちに破裂してしまうかもしれない。美鈴は一瞬そう考えて苦笑した。その笑い声が聞こえたのだろうか、パチュリーが本から顔を上げると、不機嫌とも無関心とれるような表情で美鈴を見据えた。
「美鈴…図書館になにか、ご用?」
パチュリーは美鈴を見据えたまま、抑揚の無い声で言った。まるで、さっさと用件を済ませて私に本を読ませろと言わんばかりである。
「えっと…その、咲夜さんに『寝てばかりいるのなら、本の一冊でも読んでなさい』って言われましてね…もしよかったら、本を貸してもらえないかなって…」
「そう…それなら、好きな本を持っていって良いわよ。」
「あっ、ありがとうございます…でも、どこにどんな本があるのか分からなくって…」
「奥の方にこあが居るから、彼女に聞くと良いわ。」
会話を早々と切り上げるとパチュリーは再び本に眼を戻した。それを認めると美鈴は彼女の邪魔にならないように何も言わずに頭を下げ、図書館の奥へ向けて歩き始めた。パチュリーは美鈴に対してあのような対応をしたが、決して冷たい人物ではないのだ。ただ、興味が無い事や、自らの好奇心を沸き起こさない物に対して無関心なだけなのである。偏屈であるといえば確かにそうだが、偏屈であると言うよりも知識人らしいと言った方がパチュリーには似合っているだろう。
「あれ?美鈴さんじゃないですか。一体、どうしたのですか?」
その時、頭上から落ちてきた声に美鈴は呼び止められた。ふと上を見上げると、高い書架の上部で作業をしていた小悪魔が居た。小悪魔は品の良い黒い服を着ており、とても悪魔であるとは思えない丁寧な言葉使いをする。図書館で司書の仕事をして、主であるパチュリーの補佐を務めるのが彼女の仕事であった。淡白な態度を取る図書館の主に比べ、誰にでも明るく接してくれる小悪魔は正反対の性格であった。しかし、その凸凹加減が良いのだ。きっと二人とも淡白であったら面白くないし、二人とも明るかったら図書館などは似合わないだろう。小悪魔はゆっくりと床に降り立つと、明るい笑顔を浮かべながら美鈴に言った。
「パチュリー様だったら、いつもの所に居るはずですよ?見てきましたか?」
「ええ、見てきました。パチュリー様はいつも通り、本に夢中でしたよ。」
美鈴の返答を聞くと小悪魔は、やはりそうですか、と言って微笑んだ。そして、美鈴が図書館に来た理由を聞く為に再び先程の質問を繰り返した。それに対して、美鈴は咲夜に言われたことを事細かに説明した。
「ああ、なるほど…分かりました。読む本が欲しいのですね。でも、美鈴さんはどのような本をお探しなのですか?」
美鈴は小悪魔に言われて初めて気付いた。美鈴は、どんな本を借りるか考えていなかったのである。小悪魔は美鈴の表情からそれを悟ったようであった。
「えっと…西洋魔術ならばこの棚ですし、占星術ならばひとつ向こうの棚です。悪魔召喚を学びたいのであれば…」
「あ、いや…別に魔術を学びたい訳ではないですから…そう、暇潰しになれば良いのですよ、暇潰しに…」
「ああ、それでしたら良いのがありますよ。どうぞ、こちらへ。」
笑顔で先導する小悪魔に続いて美鈴は本に囲まれた図書館を更に奥へと進んでいった。美鈴は地下にあるはずなのに、本が読める程度に明るい図書館をいつも不思議に思っていた。この疑問を小悪魔に尋ねれば、小悪魔は喜んで答えてくれるだろう。しかし、仕掛けを聞いても自分には理解出来る訳がないだろうと美鈴は考えており、明るいから明るいんだという無理やりな結論で納得していた所があった。そんな事を考えていると、先導していた小悪魔は立ち止まってひとつの書架を手で示した。
「この一角にある本ならば、美鈴さんの暇潰しに使えると思うのです。」
そういうと小悪魔は大量の本の中から一冊引き抜き、美鈴にぱらぱらと開いて見せた。その本はいわゆる図鑑であった。それは動物の図鑑らしく、外の世界の様々な地域に存在する動物が鮮やかな挿絵と膨大な文章で説明されていた。
「へぇ、凄い…こんな面白い図鑑があれば、私も居眠りをせずに過ごせそうです。」
美鈴はその素晴らしい図鑑の世界に引き込まれており、早くも図鑑を持って行きたい衝動に駆られていた。だが、小悪魔は“この一角”と言った。他にはどのような物があるのだろうか。興味を引かれた美鈴が小悪魔に尋ねると、小悪魔は別の本を先程の図鑑と同じ書架から一冊取り出して見せた。そこには、先程の図鑑と同じような鮮やかな挿絵で、今度は植物が描かれていた。
「これは、植物図鑑です。館の外に自生している植物や薬草の事を知る上で役に立つ図鑑です。美鈴さんはずっと外に居る訳ですし…この図鑑は案外役に立つのではないでしょうか?」
美鈴は小悪魔の言葉を聞いてはいたが、目の前に広げられている魅力的な図鑑に対して感嘆の声を上げる事しか出来ないでいた。
「どうぞ、持って行ってください。この本をお貸しした事は私からパチュリー様に報告いたしますので。」
そう言うと、小悪魔は美鈴に植物図鑑を手渡した。その本は大きくて頑丈で、とても重い本だった。しかし、美鈴にはその重さすら嬉しかった。
「…良いのですか?ありがとうございます、大切に読みますねっ」
「あの…そこで一つ、美鈴さんに相談したい事があるのですが…」
小悪魔は、突然に真面目な表情をして美鈴に語りかけた。その眼からは、何かを心配しているという事がまざまざと感じられた。
「こあさん、どうしたんですか?急に深刻な顔をして…」
「その…パチュリー様は前々から喘息を患っているのはご存知ですよね?近頃は症状も落ち着いて、発作もほとんど起こらなかったのですが…最近、再び症状が悪化してきたのです。」
「じゃあ、頻繁に発作が起こるように?」
「いえ、そこまで頻繁にではないのですが…でも、常に図書館に篭りっきりだから悪化してしまったのだと思うのですよ。ここは空気が埃っぽいですし…太陽に当たった方が、身体も強くなるはずですし…」
確かに図書館の空気は埃っぽかった。それは、本が大量に置かれている為に仕方が無いといえばそうなのだが、喘息に良い訳が無いのは明らかであった。また、図書館は地下にある為、太陽光が全く入ってこない。それも、パチュリーの持病を悪化させている原因であると小悪魔は考えていた。
「つまり…こあさんは、私にパチュリー様を外に連れ出して欲しいと…そういう訳ですね?」
小悪魔は美鈴の言葉を聞くと、強く頷いた。
「美鈴さんの言う通りです。パチュリー様を外に連れ出して欲しいのです…お願い、できますか?」
「任せてくださいっ、何か手を考えてみましょう!」
美鈴は力強く胸を叩いて小悪魔に約束をした。パチュリーの喘息を快方へ向かわせる為に、門番は立ち上がった。
-続-