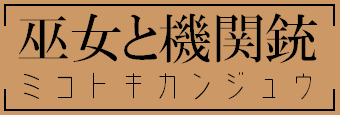日陰の魔女、或いは日向の門番 - 第二回
翌日も良い天気であった。門の前のいつもの位置に座り、暖かい日差しを受けながら借りた図鑑を眺めていた美鈴は、図鑑から顔を上げると大きく溜息をついた。先日は、小悪魔の頼みを引き受けてしまったのだが、実の所これと言って良い案は何も無いのであった。
「困りました…パチュリー様を外に連れ出すなんて…簡単じゃないですからね…」
あのパチュリーの事である。きっと生半可な理由では外に出る以前に、椅子から立つ事すらないであろう。彼女を外に連れ出すには、それ相応の理由が必要なのである。そして、その理由に彼女が応じる事で初めてパチュリーを外へ連れ出す事が出来るのだ。つまりは力任せに外に連れ出す事は不可能であるということだ。もしも、パチュリーが魔物の城に閉じ込められた姫ならば、問題は簡単である。しかし、今回の場合はパチュリー自身が魔物なのだ。
「あら、珍しい…美鈴、起きているのね。明日からは冬に逆戻りかしら。」
皮肉と驚きの入り混じった声のした方を美鈴が見ると、そこには咲夜が立っていた。美鈴の視線が向くのを確認すると、咲夜はポケットから品の良い鎖のついた銀の懐中時計を取り出して時間を確認した。
「いつもなら悠長にうたた寝をしてる時間なのに…どこか、具合でも悪い?」
「いえいえ、私は元気ですよ…さ、咲夜さんこそ、館の中の仕事が忙しいのではないですか?私なんかに構ってる暇はないでしょう?」
「この館に勤めている人材を管理するのも私の仕事だから、貴女が寝ていないかしっかりチェックするのも私の仕事の内なのよ。」
美鈴は咲夜に言われた皮肉に対して精一杯の反撃をした。だが、咲夜にかなう訳がなく、さらりと返されてしまった。落ち込む美鈴を尻目に、咲夜は美鈴の読んでいた大きな本を覗き見ると意外そうな顔をした。
「へえ、植物図鑑…また、貴女らしくない物を借りてきたのね。」
「わ、私らしくないって…私だって、図鑑くらい読みますよ…」
「まあまあ、そう怒らない。ほら、雪も解けたし、そろそろ植物も芽を出すころだから丁度いいタイミングじゃない。」
「そうですね、そろそろ花や薬草なども…」
そこまで言ったところで美鈴は閃いた。そうだ、薬草だ。パチュリーは頻繁に魔術の実験を行っている。そして、その実験の中には薬草などの植物を使う実験があるはずだ。そこで、美鈴は薬草を取りに行くという口実でパチュリーを連れ出す事を思いついたのであった。
「よしっ、思い立ったが吉日っ!早速、行動しなければ!」
雷に打たれたように飛び上がると、美鈴は門番の仕事を放り投げて走り出した。それを咲夜は呼び止める事無くただ静かに見送った。そして、美鈴の姿が見えなくなると大げさに溜息をついた。
「珍しく寝てないと思ったら…まったく、世話の焼ける門番だこと。」
咲夜の口からは美鈴に対する不満が漏れていたが、その顔には優しげな笑みが浮かんでいた。
先日は長く感じたはずの図書館へ続く階段は、今の美鈴には短く感じられた。軽やかに美鈴が階段をおりていく度に階段脇に吊るされた角灯の灯が風で揺れ、彼女の影が大きく揺れ動いていた。美鈴は最後の一段をおりると、呼吸を整えてから目の前に待ち構えている大きな扉を開いた。扉の先には相変わらず大量の書物が美鈴を見下ろしていた。その威圧感たるや、きっと咲夜が自らを睨んでいるのとさほど変わらないのではないかと美鈴は考えたが、その考えを一瞬で掻き消した。 本は睨むだけで何もしないが、咲夜は睨んだ後にナイフが飛んでくるではないか。それならば、睨むだけの本の方がかわいいに決まっている。美鈴は後ろ手で重い扉を閉めると、両側から本に睨まれながら図書館の奥を目指した。そして、美鈴はいつもの机に本を山積みにして座っているパチュリーを見つけた。その姿はさながら多くの下僕を従えた魔物の王のようであった。積み重なった本の知識を吸収し、次第に知識が肥大化していくパチュリーの姿は死体を貪ってその脊髄を啜る食屍鬼のようでもあり、美鈴は無意識の内に彼女に対して畏怖の念を抱いていた事に気がついた。しかし、脅えていても何も始まらない事は分かっている。美鈴は意を決してパチュリーに話しかけた。
「パチュリー様、こんにちは。読書中のところ、申し訳ございません…」
美鈴が言葉を発した途端に、パチュリーは本のページをめくる手を止めた。そして、視線をゆっくりと本から美鈴に移した。パチュリーは無表情であったが、その眼には明らかに読書を邪魔された事に対しての苛立ちが見えていた。
「美鈴、何の用?用事があるのなら、小悪魔に言いなさい。」
溜め息交じりに早口に言うパチュリーの言葉には、不快感を隠す気などないようだった。その言葉に圧倒されながらも、美鈴は懸命に言葉を発しなければならないと自らに言い聞かせた。
「あのっ…今日は、パチュリー様に話したい事がありまして…それで、ここへ来たのです。」
「へえ、そうなの…で、何の御用かしら?」
「ほら…その、外は暖かくなって雪も溶けましたし…そろそろ、パチュリー様が実験に使うような薬草も顔を出してきた頃ですから…それをお伝えしようと思いまして…」
「そう、ありがとう…で、それだけ?」
駄目だ、そうじゃない、報告じゃなくて提案をしなくてはいけないんだ。美鈴は自らを奮い立たせた。知識と威圧感では負けるが、気合と情熱だけはパチュリーよりも上であると思いたかった。
「いえっ、それだけではなくて…パチュリー様、もしよろしければ…中庭まで、薬草を見に行きませんか?…その、私が御一緒いたしますので。」
「へえ…そう…なら、貴女が見てきて。そして、状況を私に報告して。」
美鈴の提案を聞いてパチュリーはますます面白くなさそうな表情になったが、すぐに元の無表情に戻った。そして、再び視線を本に戻した。
「パチュリー様、外は太陽が出ていて心地良いですよ…ほら…外で本を読んだら気持ち良いのではないでしょうか?…パチュリー様、いかがですか?」
「本を外に持ち出したら日焼けするじゃない。何のために図書館が日の入らない地下にあるのか、少しは考えてみる事ね、美鈴。」
「じゃ、じゃあ…外で紅茶を飲むなんていかがですか?中庭の良い所にテーブルを置いて…咲夜さんに紅茶を入れてもらいましょう!…いかがですか?」
必死に美鈴が問いかけるが、パチュリーは無関心であった。だが、ここで退いてしまってはいけないと美鈴は考えていた。ここまで来たら背水の陣だ。
「あの、本当の所を言うとですね…この前に借りた図鑑の説明だけでは説明不足なのです。だから、パチュリー様の説明を聞きながら薬草を摘めたら、私にとっても勉強になるな…なんて、思ってまして…」
「そう…そんなに、私の説明が必要なの?」
美鈴の言葉に対して、やっとパチュリーが前向きな発言をしてくれた。ここで押さなければ、これ以降はチャンスが無いだろうと美鈴は考えた。
「ええ、必要です!」
「今の内に言っておくけれど、私の知識も本から吸収したものよ。だから、さほど役には立たないと思う。それでも良いの?」
「えっと…説明よりも、その…パチュリー様の意見が聞きたいのですよ。」
美鈴の言い分にはあまり筋が通っていなかったので、パチュリーは怪訝そうな顔をしてしばらく考え込んでいた。そして、ようやく口を開いた。
「私の意見ね…良いわ、話してあげる。」
なんとかパチュリーの承諾を取り付けた美鈴は、何故か胸が熱くなるのを感じていた。美鈴の説得は、どうやら上手く行ったようだった。その光景を書架の影からひっそりと見ていた小悪魔も、美鈴が説得に成功した事を確認して静かに胸を撫で下ろしていた。
その光景は傍から見たら異様な光景であった事に違いない。そこには、上機嫌にはしゃぎながら館の扉を開く美鈴と、彼女とは逆に冷め切った表情で玄関前のアーチに立つパチュリーの姿があった。美鈴は、はしゃぎながらも館の扉を丁寧に閉めると低い物腰でパチュリーを庭へと促した。しばらくの間、パチュリーはアーチに出来た日陰から動かなかったが、美鈴に促され渋々といった感じではあったが自らを日光の下へさらしたのであった。時刻は夕方も近い頃であったが太陽はいまだに元気にしていて、彼の目の届くところは所構わずに明るく照らし出されていた。
「いやぁ、やっぱり外は気持ちいいですね、パチュリー様!」
元気に太陽の下ではしゃぎ回る美鈴はまるで犬のようだ、そして自分にはそんな真似は決して出来ないだろうとパチュリーは思った。パチュリーは太陽が嫌いな訳ではなかった。ただ、太陽の下に出るのが苦手なだけであった。もしも、太陽が嫌いで日光に当たるだけで溶けてしまうならば、自分は魔法使いから吸血鬼に転職しなきゃいけない。そう考えてパチュリーは自嘲の笑みを浮かべると、ゆっくりと玄関先の階段をおりて、美鈴の後を追う事にした。上機嫌に鼻歌を歌いつつ先を歩く美鈴の後姿を見て、パチュリーは彼女を何処かで羨ましく感じている事に気づいた。美鈴の血色の良い健康的な肌、機敏に動く手足、そして明るい笑顔。それに比べて自分はどうであろうか、今までは薄暗い図書館に居たために目をつむってこられたが太陽の下では違いが明らかであった。
「パチュリー様?大丈夫ですか、パチュリー様?」
気がつくと美鈴が目の前に立って、心配そうな顔でパチュリーの顔を覗き込んでいた。どうやら、意識だけ何処かへ飛んでしまっていたらしい。
「大丈夫、私は大丈夫よ。」
「顔色が良くないですよ、パチュリー様…目眩でもしますか?」
顔色が良くないのは元からであったが、長らく太陽に当たってないせいだろうか酷く目眩がする事にパチュリーは気づいた。
「ちょっと、目眩がする…美鈴、腕につかまっても良いかしら?」
そのパチュリーからの要望に美鈴は快諾すると、パチュリーがつかまりやすいように腰を屈めてから腕を差し出した。彼女は一瞬だけ戸惑ったように手を伸ばしてきたが、すぐにしっかりと美鈴の腕をつかんだ。その手は冷たくて、病的なまでに白くて、美鈴には彼女が具合の悪い事を必死に隠そうとしている事がすぐにわかった。
「パチュリー様、目眩がするのであれば館に戻りますか?」
「いえ、もう少しだけ…こうやって、太陽に当たっていたい。」
「分かりました、辛くなったらいつでも言ってくださいね。」
しばらくの間、二人は寄り添いながらゆっくりと館の庭を歩き回った。そうしている間にも二人の影は伸びて、どんどんと長い影になっていった。
-続-