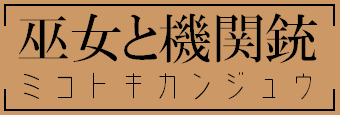日陰の魔女、或いは日向の門番 - 第三回
それから数日間、彼女達は昼過ぎになると二人で庭に出て庭を散歩しつつ植物を眺める事を続けた。ここ数日は雨も降らずにとても心地の良い天候だった為、絶好の外出日和であった。最初はあまり乗り気でなかったパチュリーも時間が経つと、美鈴と外に出る事が楽しみになってきたらしい。美鈴が図書館へ迎えに行く時刻になると、本を閉じてじっと美鈴を待っているのであった。それでもパチュリーは感情を表に出す事はあまり無く、いつも通りの無表情で美鈴に接していた。
そんなとある日の事である。その日は、今まで快晴であった空も少し機嫌が悪そうに顔をしかめ始めていた。空は半分ほど雲に覆われてしまっており、あまり気分の良い天候とはいえない日であったのだが、雨は降らないだろうと踏んだ二人はいつも通り外に散歩に出る事にしたのであった。
「パチュリー様、この草は何という植物ですか?」
美鈴はしゃがみ込んで庭に生えていた小さな葉をつけた草を指差してたずねた。パチュリーは美鈴の隣にしゃがんで、彼女の指差した草を見ると一瞬考えた後、その問いに対する答えを言うべく口を開いた。
「うん、これはハーブの一種であるセージね。この葉は乾燥させるとハーブティーにして飲む事が出来るのよ。」
「へえ…じゃあ、摘み取って後でお茶にしましょうか。」
「それも良いわね。そうそう、セージは昔から薬草として使われているのよ。ほら、外の世界に伝わっている昔の歌にもあるじゃない。」
そう言うと、パチュリーは人差し指でリズムを取りながらとある民謡の一節を歌った。美鈴はそれを静かに聴き、それからパチュリーに微笑んで見せた。パチュリーは美鈴の笑みに対して、恥ずかしげに微笑んだ。それは、美鈴が久々に見たパチュリーの笑顔だった。
「さ、さあ、もう少し歩きましょう…」
パチュリーは恥ずかしさを紛らわすために早口に捲くし立ててから立ち上がると、美鈴に背を向けてゆっくりと歩き出した。しかし、パチュリーは自らの身体の異変に気がつき足を止めた。だが、しまったと思った時にはすでに遅かった。パチュリーは突然の発作により咳が止まらなくなっていたのである。自らの意思に反するように咳は出続け、肺からは空気が急速に無くなっていった。その苦しさから立っている事すら出来なくなり、遂には地面に倒れるように屈み込んでしまった。パチュリーの横にはいつの間にか美鈴がおり、なにやら言葉を掛けている。しかし、それに答える事すらも出来なかった。パチュリーは薄れ行く意識の中で、自らの身体が持ち上げられている事に気づいた。そして、どんどんと庭が遠くなり、太陽の光が暗くなっていった。パチュリーが意識を失う前に口からこぼした言葉は、自らも予想していなかったような太陽に別れを告げる言葉であった。
パチュリーが再び目を開けると、そこは薄暗い森の中であった。どうやら身体を横たえているらしく、巨大な木々が真っ直ぐに伸びているのが見えた。そして、目の前には黒い翼を生やした悪魔がパチュリーの顔を覗き込んでいた。
「…あら、ここは地獄?そして、あなたはメフィストヘレスか何か?」
その声を聞いて悪魔は微笑んだ。そして、優しげな声で言うのだ。
「よかった…パチュリー様が無事で…」
そんな優しい声で誘惑する悪魔はどの程度存在しただろうか。パチュリーは頭の中を探ってみたが、そんな悪魔など掃いて捨てるほどいた。しかし、こんなに真剣に心配してくれる悪魔はたった一人しかいない。
「…こあ、私は大丈夫。迷惑を掛けたわね。」
そこは見慣れた図書館の中であった。そして、目の前にいる悪魔は図書館の司書である小悪魔に他ならない。しかし、先ほどまで一緒に居たはずの美鈴の姿は見えなかった。そこで、パチュリーは小悪魔に聞いてみる事にした。すると、美鈴はパチュリーをここまで連れてきた後すぐに仕事に戻った、と小悪魔は言った。
「じゃあ、パチュリー様…私は整理の仕事に戻りますので、何かあったら呼んでくださいね。」
小悪魔が去ると、パチュリーの周りには誰も居なくなった。そこには薄暗い空間に置かれた大量の本があるだけで―これは、パチュリー自身でも意外であったのだが―自分が何か心寂しく感じている事に気づいたのであった。普段ならば静かなこの空間が一番心地良いはずなのに、きっと太陽の光に当たったせいに違いない。パチュリーはそう考えると何故か笑いがこみ上げてくるのを感じた。
「馬鹿みたいな話、日陰でしか生きられない魔女が太陽を恋しがるなんて…こんな筋書き、三文小説でもやらないわね。」
パチュリーは横たわったまま腕を額の上に乗せて声を殺して笑うと、ゆっくりと起き上がり溜め息をついた。
整理の仕事に戻るといった小悪魔は、今まで整理をしていた書架に目もくれずに通り過ぎると真っ直ぐに図書館の出入り口である大きな扉の前まで来た。そこには扉に寄りかかって心配そうな顔をしている美鈴の姿があった。美鈴は歩いてくる小悪魔の姿を見つけると、すぐに走り寄って彼女の言葉を待った。
「美鈴さん、パチュリー様は大丈夫です。発作も治まりましたし、すぐに元気になるでしょう。」
小悪魔の報告を聞くと、美鈴は胸を撫で下ろして今まで呼吸が出来なかったかのように大きく息を吐いた。
「よかった、一時はどうなる事かと…もう私、泣きそうになっちゃって。」
そう言って美鈴は恥ずかしそうに頭を掻いて見せたが、その眼は赤くなっていて小悪魔には美鈴が泣いていたのだとすぐに分かった。
「美鈴さん、明日はどうされます?明日もいつもの時刻にパチュリー様を迎えに来ますか?…明日にはパチュリー様の体調も良くなっていると思いますので。」
小悪魔の問いを聞くと、美鈴の顔には不安げな表情が浮かんだ。
「もし、パチュリー様が行くと言ったら…でも、今日みたいな事がまた起こるかと思うと…」
「大丈夫です。パチュリー様の体調は徐々に良くなって来ています。ここ最近なんて、美鈴さんが迎えに来るのを楽しみにして待っていたのですよ…ですから、ね?もう少しの間、予定通りにお願いします。」
「え、ええ…わかりました。では、明日もいつもの時間に…」
美鈴の言葉は彼女達の背後から聞こえた物音にさえぎられてしまった。彼女達が音のした方を向くと、そこにはパチュリーが書架にもたれる様にして静かに立っていた。
「あらあら、お邪魔だったかしら?貴女達の…密会の途中に。」
密会、パチュリーの口から発せられたその言葉が何やら重々しく美鈴と小悪魔に圧し掛かってきた。小悪魔はパチュリーに弁解しようと口を開きかけたが、それは彼女の手で阻止されてしまった。
「何やら美鈴が熱心に私に頼むものだから、本当に私の知識を必要としているのかと思ってしまったわ。まあ、普段そんな事なかったんだし、それを真に受けた私が馬鹿だったのでしょうけど。」
パチュリーの顔に笑みは浮かんでおらず、ただ無表情で淡々と語るだけであった。その表情に、美鈴はパチュリーを説得しに来た時に彼女が浮かべた表情よりも冷たいという印象を受けた。
「美鈴、貴女はもう来なくて良いわ。私は所詮、日陰でしか生きていけないのよ。貴女たちがどんなに私を穴倉から引っ張り出そうとしても…私は…」
その言葉を発したとき、パチュリーの無表情であった眼が揺らいだと小悪魔は感じた。しかし、パチュリーは再び元の無表情に戻ると二人を一瞥した後に背を向けた。
「ねえ、こあ。貴女、仕事が終わってないんじゃないの?このままだと寝る時間が無くなるわよ。」
パチュリーは小悪魔に事務的に言い放つと図書館の奥へと戻って行った。しかし、その言葉はあまりにも事務的すぎた。抑揚が無く、ただ言っただけの言葉。それが逆に、小悪魔には何処か引っかかるものがあった。
パチュリーは自らが発した言葉が、いかに酷い言葉だったか理解していた。今まで自らに対して尽くしてくれた小悪魔に対しても、自らの事を心配して行動してくれた美鈴に対しても。それが痛い程に分かっている為、歩もうとしても足は鉛になってしまったかのように重く、胸は石を飲み込んでしまったかのように苦しくて辛かった。パチュリーは歩こうと努力をしていたが一向に前に進んでいる気はせず、ずっと同じ書架の前で立ち止まっているかのような感覚に襲われていた。しかし、それは錯覚に過ぎず実際はゆっくりとではあるが身体は進んでいた。そして、ようやくいつもの机までたどり着くと、パチュリーは崩れるように座り込んで顔を机に伏せた。使い込まれた机は冷たくて、それでいて少し温かくて妙な感じだった。もしかしたら、この机よりも自分の方が冷たいかもしれない。そう考えるとパチュリーは、急に悲しくなって気持ちが更に沈んでいくのが分かった。あんな事、本当は言いたくなかった。では、本当は何と言うつもりだったのか。パチュリーは自問したが答えは浮かんでこなかった。 その間も気持ちは沈み続け、深い海の中のように暗くなり、光が周りから消えて、そして、海底はどこにあるのか分からない程の深遠へと沈んでいった。
パチュリーが去った後、美鈴は何度も謝罪する小悪魔に笑顔で別れを告げると、図書館を後にした。図書館の扉が閉じて薄暗い廊下にたった独りで居ると、彼女は胸が痛くなる程の孤独感を感じた。苦しさに耐えられなくなった彼女は、階段を逃げるように駆け上がると、門へ戻る為に玄関へと向かった。重く冷たい玄関の扉を開けると外には雨が降っていた。先ほどまで空の半分を占めていた雲が頭上を厚く覆ってしまっており、その黒く鈍重そうな雲から音を立てて雨が降っている。 美鈴は玄関脇にかけてある黒いレインコートを取ると、それを素早く羽織った。ゴム引きのレインコートは重くて肩に圧し掛かって来たが、今の美鈴の心境に比べれば別段負担になるような重さではなかった。美鈴はレインコートのボタンを全て留めると、コートについている大きなフードを頭に被り外に出た。「こんな酷い雨になるなんて、本を返しておいて良かったかもしれない」と美鈴は思った。だが、それは一方で完全に身を引くという事であると美鈴は理解していた。一歩外に出ると、外の世界は雨音に支配されていた。周りから聞こえるのは地面に雨が落ちる音や、水面を雨が打つ音、堅いレンガを雨が打つ音、そんな音ばかりだった。しかし、そこに美鈴が石畳の道を歩く音が加わる。すると、雨の音ばかりだった世界は途端に美鈴の足音を異端扱いし始めるのだった。
美鈴は両手をレインコートのポケットにしっかりと差し入れ、中で強く手を握り締めた。レインコートを着ていても雨は冷たい。特にこの季節の雨は寒くて、あまり心地の良いものではない。結局は自分の力不足だったのだ。もしも、別の方法でパチュリーを連れ出そうとしたら、今回のような結末にはならなかったのではないか。だが、そんな事を考えても遅い、もう終わった事なのだ。 それは美鈴にもとっくに分かっている事だった。しかし、美鈴にはその考えを止める事が出来なかった。
-続-