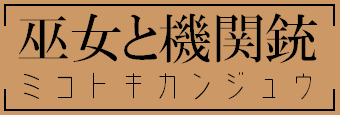日陰の魔女、或いは日向の門番 - 最終回
その翌日も雨だった。空を覆った鈍重な雲が身体を退かそうとする気配は一向になさそうで、太陽の光は地面に届く前に意地悪な雲にさえぎられてしまっていた。そのお陰で館の周りには何やら鬱々とした雰囲気が漂っていた。そして、その雨のもたらす陰鬱な空気は地下にも染み出してきており、普段から薄暗い図書館もなお一層のこと薄暗くなっているように感じられた。
雨のもたらす陰鬱な雰囲気が後ろから不安を煽っている。小悪魔は遅々として作業が進まない事に溜め息をついた。そして、いつもの机に座っているパチュリーを心配そうに遠くから見つめた。小悪魔は今朝からずっとあのまま動かないパチュリーを心配していたが、彼女自身どう動いて良いものか決めかねていた。一方の自分はパチュリーに話しかけようとしているが、もう一方の自分はしばらく距離を置いて見ているだけの方が良いと告げている。確かに、遠くから見物しているだけの方が圧倒的に楽だろう。しかし、それだけでは事態は何も動かない。それどころか、このまま深く沈んでしまって何処かの海溝で動けなくなるのが結末だ。しかし、そんな結末は小悪魔の望んでいる結末では無い。小悪魔は自らの中で起こっていた議論に終止符を打つと、行動を起こすべく図書館の奥へと足を進めた。
パチュリーの身体は確かにそこに存在していた。それはパチュリー自身でも感じている事であった。しかし、精神は何処か別の場所へ飛んでいる。いや、飛んでいるのではない、実際には沈んでいるのだ。遥か頭上に自らの身体が見えるが、そこへは浮かんで行けずに、ただただ精神がゆっくりと沈んで行くのを受け入れるしかなかった。パチュリーは沈んでいく最中、もしもこのまま沈んで精神が消えてしまったら、自分の身体はどうなるのだろうかと考えてみた。そうなったら、身体は抜け殻になってしまうに違いない。生きてはいるが、何も言わず、何も見えず、何も感じないだろう。だが、果たしてそれで生きていると言えるのだろうか。少なくともパチュリーはそう思わなかった。しかし、別にそれでも構わないと感じていた。精神が消えてしまえば苦痛を感じる事はなくなるだろう、それがどんな痛みでも。そして、パチュリーはそのまま沈む方を選んだ。パチュリーが眼を閉じて流れに委ねると、精神は更に深く沈みこんでいった。が、その時、誰かがパチュリーの精神を浮上させた。そして、あっという間に現実へと引き戻されていった。
「パチュリー様?申し訳ございせん、お話があるのですが…」
そこには胸に大判の本を抱えた小悪魔がいた。パチュリーの精神を浮上させたのは小悪魔だったのである。やはり、精神と身体というのは簡単に切り離せるものではないらしい。パチュリーは内心で落胆するのと同時に何やら安堵の気持ちも覚えていた。
「どうしたの?作業は終わったのかしら?」
パチュリーは、片手で髪をかき上げると気だるそうに言った。
「あ、その…作業はまだなのですが、パチュリー様にお話したい事が…」
小悪魔は必死に言葉を選び出して話しているようであった。パチュリーは何も言わずに小悪魔が言葉を続けるのを待った。
「その…昨日は、申し訳ありませんでした…結果的にパチュリー様を騙すような事をしてしまって、本当に申し訳ないと…思っています。」
深々と頭を下げる小悪魔をパチュリーはじっと見ていた。何も言わずに。
「でも、美鈴さんは何も悪くないのです。ですから、美鈴さんの事は赦してあげてください。今回の出来事は全て…」
「分かっている。全て、貴女が考えた事なのでしょ?」
パチュリーの言葉に小悪魔は驚いて、はっと息を呑んだ。
「分かっている。いえ、分かっていたつもりだったのかもしれない。それは今でも分からない…でも、私は貴女たちに感謝している。本当に感謝しているわ。」
小悪魔にはパチュリーの口から出た言葉に嘘は無い事が分かった。パチュリーは本当にそう思っているに違いない。そして、一呼吸置くとパチュリーは言葉を続けた。
「美鈴と一緒に外に行くのはすごく楽しくて、毎日楽しみだった。でも、私は…私が倒れた日に気づいたの。私自身が太陽を欲している事に。信じられないでしょ?日陰女が日向に出たがっているなんて。」
パチュリーは自嘲めいた笑い声を上げると、すぐに元の真面目な表情に戻った。その顔には、悲しさと恐怖心の入り混じった表情が浮かんでいた。
「私にはそれが信じられなかった。そして、怖かったわ。自分が変わってゆく事が。怖くて、怖くてたまらなかった。だから、これ以上変わってはいけないんだって自分に言い聞かせて…貴女に相談しようと思ったの。でも、そしたら貴女と美鈴が話しているのが聞こえて、それで事の次第を知ったの。その時は、あんな事をいうつもりは無かったんだけど、私の心は恐怖でいっぱいで…きっと恐怖心が怒りを後押ししたんだと思う。気がついたら、貴女たちに対してあんな事を言っていたわ。」
まるで、子供が悪戯を咎められて弁解をしているような口調でパチュリーは語った。パチュリーが話している間、今度は小悪魔が何も言わず静かに話を聴いていた。
「もちろん、そんな言い分なんて通る訳ないし、ただの言い訳だってわかってる。私は酷い事をしたわ。だから、私は貴女たちに、どんなに責められようとも…」
それまで何も言わずに聴いていた小悪魔であったが、そこで静かに彼女を制止すると優しく微笑んだ。小悪魔には分かっていた。彼女の内側に恐怖心があったという事が。それは、あの時にパチュリーの眼を見た時から気づいていた事だった。あの時のパチュリーの眼は、恐怖で震えていたのだから。
「お止めください。私はパチュリー様を責めたりなんてしませんよ。もちろん、美鈴さんだってそんな事は望んでないでしょう。だから、自分を責めるのは止めて下さい…ね、パチュリー様。私は、パチュリー様が苦しんでいる所など見たくはないのです。」
小悪魔は、パチュリーに対して精一杯の笑顔で優しい言葉をかけた。小悪魔の言葉を聞くとパチュリーは一瞬はっとした表情を浮かべた。小悪魔に責められるに違いないとばかり考えていたから、パチュリーにとって小悪魔の優しい言葉は予想外だったのだろう。小悪魔は抱えていた本を机の上に置いてポケットから小さなハンカチを取り出すと、俯きながらすすり泣いているパチュリーの手に握らせた。そして、小悪魔は静かに彼女の肩に手を回しゆっくりと抱擁した。優しい悪魔の抱擁はしばらくの間続いていた。
長らく降り続いた雨も上がり、空に居座っていた雲も何処かへ動いてくれた。やっと出来た雲間から太陽の顔が見えるようになり、太陽も満足げな表情を浮かべているように思えた。美鈴はレインコートのフードをあげると、全身についた雨を手で叩き落した。レインコートを叩く度に水滴が舞い上がり、細かい水の粒が太陽光を受けてきらきらと光輝いている。
「雨、上がったわね。」
美鈴は、光り輝く水滴の向こうから聞こえる声に気付くと手を止めて顔を上げた。すると、そこには見覚えのある大判の本を抱えたパチュリーの姿があった。彼女は気まずそうな表情を浮かべ、門の脇にひっそりと立っていた。
「美鈴、昨日は本当に…」
「パチュリー様、何の御用ですか?私は忙しいのですから、手短にお願いしますね。」
美鈴はパチュリーが言い終わらない内に、妙に演技がかったむすっと表情をして言って見せた。しかし、自分の演技があまりにも滑稽に思えてしまって、美鈴は数秒も立たない内に笑ってしまっていた。そして、それに続くように彼女も一緒に笑っていた。しばらく笑った後、先に口を開いたのは美鈴であった。
「今日は暖かいですね。まだ地面は乾いてませんが、絶好の散歩日和ですよ。ご一緒にいかがですか、パチュリー様?」
その問いかけにパチュリーは赤面しつつ微笑みながら、首をゆっくりと立てに振った。そして、抱えていた大判の本を美鈴に差し出すと上目遣いで遠慮がちに言った。
「これ…貴女に貸していた図鑑。貴女が良ければ、まだ借りていて欲しいのだけれど。」
差し出された本を受け取ると、美鈴はパチュリーに対して礼を言った。それを聞くと、パチュリーは再びゆっくりと頷いた。そして、二人は雨のやんだ庭を歩き始めた。庭に敷かれた芝には雨の滴がついていて、光を反射して輝いて見えた。辺りには物音がせず、二人の足音と静かにそよぐ風の音だけが聞こえていた。二人はしばらくの間、何も言わずに歩いていたが、不意にパチュリーが口を開いた。
「美鈴、腕につかまっても…良い?」
その問いに美鈴は快く応じると、パチュリーに腕を差し出した。もちろん、彼女が腕を取りやすいように、少し腰を屈めてから。控えめに美鈴の腕をつかんできたパチュリーの手は、美しく温かい手であった。
-終-