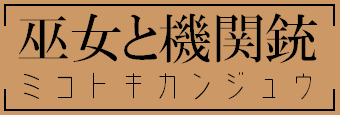憂鬱はインクの染みのように
何も書かれていない白い紙の上を、金色の靴を履いた万年筆が軽やかな足取りで踊るように流れて行く。万年筆の通った所が黒い跡になって残り、それが文字となって白い紙に刻まれて行く。そして、その文字達は終止符によって締めくくられ、一つの文章となるのである。だが、休む間も無く万年筆は踊り続けるのだ。一枚の紙の上を端から端へと渡り歩き終止符を打つと、次の行へ向かい再び踊り始める。万年筆を掴む小さな手は休む事無く動き続け、淡々と文字を紙に写し続ける姿はあまりにも機械的であるように見えた。彼女の周りは静寂に包まれ、聞こえるのは万年筆が紙を擦る音と、微かに聞こえる整った呼吸の音だけであった。使い込まれた古い机の上に置かれた洋灯の灯がほのかに揺れ、彼女の影を消えかけた幻燈のように紅い絨毯の上に映し出していた。
紙の上を半分ほど過ぎた頃だろうか、万年筆の舞踏は突如として終わりを告げた。ペンの通り道についていた黒い跡は擦れてしまい、今まで流れるように続いていた線は干上がった川のように切れ切れになってしまっていた。作業を中断された彼女は少々機嫌を損ねたようで、持っていた万年筆を机の上に置くと、大きな溜息をついた。そして、万年筆にインクを充填する為に机の上方へ手を伸ばすと、小さなガラスの小瓶を手に取った。その小瓶の中にはインクが入っているはずであったのだが、彼女の予想に反して小瓶は軽く、否が応にも中は空である事が分かった。そこで、彼女は手に持った小瓶を机の上に置くと、自らの使い魔である小悪魔を呼ぶことにした。
「こあ、インクが切れたわ。換えのインクを持ってきて欲しいのだけれど。」
彼女の呼び声は図書館に小さく響いたが、その声はすぐに静寂に飲み込まれてしまい、元の静けさが辺りを再び包み込んだ。いつもならばすぐに現れるはずの小悪魔であったが、今日に限って姿を現すどころか返事すらしなかった。彼女は少々不審に思ったが、きっと書架の整理が忙しいに違いないと結論付け、作業をしていた本を閉じると自ら重い腰を上げる事にした。
彼女が一歩足を進めるたびに、足が床に敷かれた真紅色の絨毯を擦って音をたてた。その微かな音さえも大きく聞こえるほど静まり返った図書館の中は、空気さえも声を潜めているかのようだった。しかし、それは彼女にとってはいつも通りの事なのだから、別段気にする事もないのだろう。周囲に何も聞こえない書架の間を歩いている姿は、魔女である彼女を更に怪しいものにしていた。今、彼女の周りに見えるのは整理された本だけだった。全てが収まるべき所に収まり、全てが整頓された書架。彼女にとってこれらの本は無くてはならないものであると同時に、彼女そのものでもあった。それは、彼女の知識は全て本から吸収したものであり、本は全ての知識の源だからである。彼女は常に本を読み、本を持ち、本と共に居る。それが彼女にとって普通であったし、それ以外は彼女にとっても考えられる事ではなかった。
図書館と外界を遮断する巨大な重い両開きの扉を開けると、彼女は図書館の外へ出た。扉を抜けるとそこは階段であり、緩い傾斜の階段が地上まで続いている。だが、明かりは壁に取り付けられた角灯だけである為、先が見えない階段はどこまでも続いているかのようだった。薄暗い階段を、彼女は一段ずつゆっくりと登っていく。この階段も静かで、角灯の炎が静かに燃えている音と彼女の足音しか聞こえず、あたかもこの館には彼女以外の者は居ないのではないかという錯覚さえ覚える程であった。
階段を上りきった先の扉を開けると、そこは暗がりの広がる廊下であった。この館は窓が極端に少ない。その為に、地上であっても地下と同じで蝋燭の明かりが欠かせないのである。等間隔に壁につけられた燭台には灯が点されており、廊下を微かに照らしていた。地上に出た彼女はまず、普段から使っている居間へと向かう事にした。そこへ行けば咲夜が居るはずだと彼女は考えたのだ。メイド長である咲夜ならば、インクの在り処も分かるはずである。
居間はいつものように綺麗であった。上品な色合いの絨毯は丁寧に掃かれており、一点たりとも埃が積もっている所などは無かった。寒い季節が終わって火を入れる事がなくなった暖炉も、綺麗に煤を取り除かれている。彼女は居間の中を見渡したが、咲夜の姿がどこにも見えなかったので、少々落胆した。これではどうする事も出来ない、いっそのこと図書館へ戻ろうか、などと彼女はどうしたら良いものかとあぐねていると、居間の扉が開いて誰かが入ってくる気配がした為、彼女は扉の方へと振り向いた。すると、そこには彼女が今まで探していた咲夜の姿があった。
「あら、パチュリー様。いかがされました?」
咲夜は手に花を活けた花瓶を持って、扉の前に立っていた。咲夜を見た彼女は、貴女を探していたのだと告げると、咲夜は微笑んで、何の御用でしょうか?と訊ねた。
「実は、筆記に使っている万年筆のインクが切れてしまったの。こあに持ってくるように頼もうと思ったのだけれど、彼女も手が離せないみたいでね…そこで、貴女に頼もうと思って出てきたのよ。」
「かしこまりました。すぐにお持ちしますので、少々お待ちくださいませ。」
咲夜は花瓶をテーブルの上に飾ると、一礼をしてインクを探しに部屋から出て行った。扉が完全に閉じて咲夜の姿が見えなくなると、彼女は花瓶の置かれたテーブルの脇に置いてある座り心地の良さそうな椅子に腰を下ろして一息ついた。そこで彼女は、ふと気付いた。いつも持ち歩いている本を図書館に置きっぱなしにしていたのである。それには彼女も落ち込んだが、もう一度戻って取りに行くのも面倒な話である。どうせ、咲夜の事であるからすぐに戻ってくるだろうと踏んで、彼女は本の事を暫しの間忘れる事にした。
この部屋の中も他の場所と同じで、とても静かだった。蓄音機は針が上がっており、大きなホーンからは何の音楽も流れては来ず、唯一の音といえば部屋の脇に置かれた振り子時計が立てる微かな音だけであった。椅子の柔らかいクッションに身体を委ねてまったく身動きせずに、静かに一定の間隔で揺れ続ける時計の振り子を見ている彼女のその姿は、あたかも部屋に飾られた舶来の人形のようにも見えた。所々に配置された照明が室内を仄明るくしており、その薄暗さは少々過度なものであったが、ここの住人にとってそれは嬉しい事であるので、なんら不都合な事はなにも無いのである。ただ、外からの訪問者があると、彼らは決まって言うのだった。この館は不気味で近寄りがたい、と。
どれほど前の事だっただろうか、彼女は館の主人に「貴女は人を殺めた事があるの?」と尋ねてみた事があった。その問いに対し、主人は言った。
「さあ、どうかしらねぇ…じゃあ、聞くけど。何かを殺めた事の無い、そんな聖人みたいな人なんていると思う?」
主人に問い掛けると、新たな問いが飛んで来るのは良くある事であった。今回の問い掛けも、主人の挑戦的な目線と意地悪な笑みと共に彼女に戻ってきた。
「そんな人も、居たって良いじゃないのかしら?世の中に、一人くらいは。」
彼女がそう答えると、主人は甲高い声を上げて笑い始めた。そして、笑いが収まると、再び意地悪な笑みを顔一杯に湛えて言うのだった。
「居る訳が無いじゃない。聖人面をした人なら何処にでもいるけど、本当の聖人なんて御伽噺の中にしか存在しないわよ。」
あまりにも嫌味がかった主人の台詞に少々憤りを感じてしまった彼女は、そっけない態度を装って主人に言い返したものである。
「あらそう、貴女は夢が無いのね。」
それに対して主人は、
「夢に生き過ぎるのも良くないわよ。行き過ぎた夢は人を壊してしまうから。」
と意地悪で悪意に満ちた、けれども何処か幼い無邪気なものを感じる笑みを浮かべながら言ったものである。しかし、納得の行かなかった彼女は、主人を問い詰めてみる事にしたのだ。
「何も殺めた事の無い聖人なんて居ないのなら、貴女だってもちろん聖人じゃないわよね。だったら、吸血鬼として必要な血を手に入れる為に、人を殺めた事があると解釈しても良いのでしょ?」
だが、この時、どうやら装っていた態度が見抜かれてしまったらしい。主人は、ねっとりと絡みついてくるような視線で彼女を見つめていた。
「あら、パチェ。今日はやたらと感情的になっているのねぇ…どうしたの?」
「私はいつも通りよ、レミィ。それよりも、私の問いに答えて頂戴。」
後になって彼女は後悔したのだが、この時は主人の指摘通り、やたらと感情的になりすぎていた。しかし、何故なのかは今でも分からない。きっと、単なる気の迷いだったのだろう。だが、気の迷いというものは、時に望む事のない不利益すらもたらす事がある。主人は笑みを浮かべたまま、彼女の顔をじっと覗いていた。そして、仕方が無いというようにゆっくりと口を開いた。
「そうね、貴女の言う通りかもしれないわねぇ…だけれど、血は少しだけあればいいの。ティーカップ一杯、それで十分よ。殺してしまう程の血は、私にとって必要ないものだわ。」
彼女は何も言わずに、主人の次の言葉を待った。主人の言葉には含みがあるような気がして、彼女のどこかに引っ掛かっていたからだ。
「ただ…私は後片付けをしなくて良いから、すごく楽なのよ。要らないモノの後片付けは全部、私の優秀な従者がしてくれるもの。」
要らないモノの後片付け。それが意味する所を、彼女は容易に理解できた。彼女は、この時ほど吸血鬼という存在が恐ろしく感じた事は無かった。それは、ただ恐怖を感じただけだからではなく、その後ろに潜む何らかの大きな闇を覗き見てしまった気がしたからかもしれない。この館の主人は、ただの吸血鬼では無いのだ。命令に躊躇い無く従う"犬"が側にいるのである。もし、主人が殺せと命令したら…いや、この主人が直接的な命令を下す事など、そう無いだろう…しかし、命令があれば無慈悲に相手を始末するに違いない。それが、いかに親しい間柄だとしても、主人の命令ならば。
主人は指を立てて従者を呼ぶと、椅子の横に跪くように指示をした。忠実なる従者は、自らの崇敬する主人の脇に跪くと何も言わずに命令を待っていた。主人は鋭い爪のある指で静かに従者の顔を撫で、軽く顎を掴むと自らの方へと引き寄せた。そして、人の肌など容易に貫いてしまう事の出来る尖った牙を持った小さな口を開き、従者の耳元で言うのだった。
「いっぱいお喋りをしたから、喉が渇いたわ。咲夜、お茶を頂戴。」
そこまで考えた所で、彼女はいかに自分が恐ろしく下らない想像をしているのかに気付いた。あまりにも馬鹿馬鹿しい想像ではないか。軽く頭を振ってその考えを振り払うと、彼女は溜息をついた。彼女は、この館の主人を決して嫌っている訳では無いし、恐れている訳でもない。ただ、吸血鬼という種族の印象そのものが、そのような考えを抱かせてしまうのに十分すぎる動機になっているのだ。やはり、手元に本がないと妙な事ばかり考えてしまう。
「パチュリー様、お待たせいたしました。」
突然、背後から聞こえた声に彼女の身体が緊張と驚きで一瞬痙攣を起こした。彼女は、すぐさま後ろを振り向くと、そこには静かに佇む"犬"…もとい、吸血鬼の従者の姿があった。
「申し訳御座いません、驚かせてしまいましたか…?」
「いえ、大丈夫…突然、声が聞こえて驚いただけだから…それで咲夜、インクは…あったの?」
彼女は平静を装い会話をしたが、明らかに動悸が激しくなっているのが服の上からでも分かるほどであった。
「それが、どうやら蓄えが無いらしく倉庫を調べてみたのですが、見当たりませんでした。どうしても必要ならば、遣いの者を出して購入させて来ますが…」
「いえ、結構よ…無いのだったら、仕方が無いから。咲夜、ありがとう。」
彼女は礼を述べると椅子から立ち上がり、図書館へ帰るべく居間を後にした。彼女が扉を完全に閉めるまで、従者は一歩たりとも動かずに彼女が立ち去るのを見送っていた。扉を閉め、廊下に独りきりになると、ようやく動悸が治まったのを感じた。しかし、心の底に妙な不安感が居座っており、彼女の足取りは重いままであった。
黒く不気味な眼窩のように、暗い中を続く廊下が目の前に伸びている。この廊下を歩まねば、自らの目指す図書館へは帰れない。彼女は意を決すると、一歩ずつゆっくりとした足取りで歩を進めた。だが、その暗闇が彼女にとっては恐怖の対象になりつつあった。それまでは何とも思わなかったはずの暗闇が、今はただ悪戯に不安感を募らせるだけのものでしかなくなっていた。「私には、優秀な従者が居るのよ。」そんな主人の言葉が頭を掠めていった。彼女は、そのような存在が自分には居るのだろうかと考えた。優秀な従者なんて、そんな大それたものは必要ない。ただ、いつも横に居て支えてくれる存在、彼女にはそれで十分であった。彼女には、心当たりが無い訳ではなかった。ただ、確かめるのが怖かったのだ。もしも、否定されたらどうするのか、それは彼女とって到底耐えられる事ではない。問うのは容易であるが、その答えを聞くのは並大抵の勇気では足りないものがある。それが、毎日を共に生活をし、仕事をし、楽しい事も、悲しい事も分かち合ってきた人物ならば尚更だろう。それが分かっているから、彼女は確かめる事が出来ないのだった。
彼女は、地下の無名都市へと続くかと思われるほどに長く暗い階段を下りると、やっとの思いで図書館の重い扉を開けた。埃臭い古い紙とインクの匂いに安堵し、いつもの位置にある机へと戻ると、机の上は先ほど席を立った時のままであった。本は机の上に無造作に置いてあり、書きかけの紙と脇に置かれた万年筆も同じ位置にあった。それは極々当たり前の事であるのだが、今の彼女にとっては何よりも心を落ち着かせてくれる事であった。しかし、彼女は席に着こうとした際に気付いた。一つだけ、席を立ったときと違うものがあったのである。席を立つ前に空の小瓶が置いてあった場所に、今はなみなみと黒い液体が入って封のされている小瓶が置いてあったのだ。彼女は、小瓶を見つけた咲夜が持ってきてくれたのかも知れないと考えたが、すぐにその考えを否定した。その小瓶は、彼女が今まで抱いてきた不安な気持ちを吹き飛ばしてしまうのに、十分すぎるものであったのだ。そして、小瓶を取って暫しそれを眺めた後、ぽつりと彼女は呟いた。
「ありがとう、小悪魔。大切に使うわね。」
彼女には分かったのである、その小瓶は小悪魔が持ってきてくれた物であると。この広い図書館の何処かで仕事をしている小悪魔の気配が、彼女には感じられたのであった。
-終-