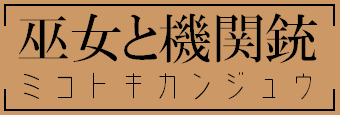短々編06 - 彼の姿は白黒写真のように
目を開けると辺りは真っ白な景色に覆われた世界だった。地上にある物は全て白く、見渡す限りどこまでも白い景色が広がっていた。しかし、ただ白いだけではなかった。その世界は白く輝いていたのだ。まるで、宝石のように光り輝いている世界。そんな世界は今まで一度も見た事がなかった。
私は、真っ白な世界を見ているのが眩しくなり少し視線を上げた。するとそこは、一転して真っ暗な世界だった。頭上にはどこまでも続いている暗闇が存在していた。だが、その暗闇の中に何千何万という数え切れない程の光の点が見えていた。それは、真っ黒なクロスの上にダイヤモンドを散りばめたかのようにも見えて、幻想的であると同時に何やら吸い込まれそうにもなる程の魅力を持っていた。
「ここは…何処?」
私は思わず口に出してしまった。つい先程まで図書館に居た筈だったのに、気付けばこんな見ず知らずの世界に居る。
「こあ?何処にいるの?まさか、悪戯をしているんじゃないでしょうね?」
多少の混乱と共に私の口から出た言葉ですら、頭上の暗闇に吸い込まれてただの音波の反響に成り果ててしまったようだった。もはや溜息すらも波の揺らぎ程度にしか感じられず、こんな広い世界に私は独りなのではないかと思い始めていた。
「どなたか、お探しなのですか?」
何処からか声が聞こえた。それは、雑音の混じったとても明瞭とは言えない声だったが、今の私にとっては心強く感じられる物だった。
「誰か…居るの?」
「はい、ここに居ります。」
「誰か居るのね?じゃあ、あなたに聞くわ…ここは、何処?」
私の問い掛けに声の主はしばらくの間、耳障りな雑音だけをあげていた。そして、再び明瞭とは言えぬ聞き取り難い声を出した。
「この場所は、雨の海と呼ばれています。」
それは何処かで聞いた事のある地名だった。だけど、何処で聞いたのかを思い出す事よりも先に、私はその名前に疑問を感じてしまっていた。声の主は海だと言うのに、ここには水が一滴もないじゃないか。
「とりあえず、雰囲気から幻想郷ではないというのは分かるわ。だけど…何故、海なの?水なんて何処にも無いじゃない。」
「申し訳御座いません。その質問に対して、お答えする事は出来ません。」
自らの質問に答えてもらえなかった事に落胆とも怒りとも分からぬ感情を覚えてしまった私は、大きなわざとらしい溜息をつくと声の主に再び問い掛けてみた。
「あら、そう…じゃあ、そろそろ私を幻想郷に戻して頂戴。」
「申し訳御座いません。幻想郷という地名は確認できません。」
「あなた…何処にいるのか知らないけど、ふざけるのは止してくれないかしら?」
気付けば混乱していた事もあって、私は姿の見えぬ声の主に対して声を荒げていた。すると、その声の主は雑音だけを発したまま黙っており、しばらく経ってから再び聞き取り難い声を出した。
「私はずっと貴女の下に居ります。貴女は私の上に座っているのですよ。」
その言葉に私は少々驚いて自らの座っている場所を確認した。今まで気付かなかったが、そこは光を反射して輝く丸い板の上だったのだ。その板は表面がごつごつしていて、あまり座り心地は良くなかった。私は板の脇から下を覗き込んでみると、これまた光沢のある丼のような体に車輪が全部で8つばかり付いているのが見えた。
「これは、何かの乗り物ね?…あなたは、この中に乗っているのね?」
「はい、そうです。まあ、多少の語弊があるかもしれませんが。」
声の主はこの光沢のある乗り物に乗っていた。とりあえず、物事が一歩進んだ。だけど、それが分かった所で私は幻想郷へは戻れないのだ。こんな何も無い白い世界で、私は顔も見えない誰かと一緒にこれから過ごさねばならないのだ。私は一気に失望してしまった。もう二度と、小悪魔の淹れた紅茶を飲む事は出来ないのだろうか。ふと小悪魔の顔が脳裏をよぎり、私は周囲の世界がぼんやりとぼやけてゆくのを感じた。すると、私が落ち込んでいる事に気付いたのだろうか、例の声の主が再び雑音を立て始めた。
「貴女は心配しなくても、元の世界に戻る事が出来ます。確率的にはそうなっています。」
もっと気の利いた言い方はないのだろうか。その不器用さに私はついつい笑ってしまった。
「確率的ね…あなた、もっと良い励まし方はないの?」
「すみません、気が利かなくて…では、これではどうでしょうか?私のカメラの向いている方向を見てください。」
私は袖で微かに潤んだ眼を拭うと、声の主の言うカメラを探した。私はカメラの存在を本で読んで知っていたし、いつも飛び回っている新聞屋が使っているのを眼にしていたからすぐに見つける自信があった。だが、そこに付いているのは一目見ただけではカメラとは気付かない物であった。
「これが、あなたのカメラなの?」
私はその声の主が言うカメラを覗き込んでみたが、それは光沢のある板に囲まれて出っ張っていて、私には昆虫の目玉のようにすら見えた。
「はい、それが私のカメラです。貴女の姿が良く確認出来ますよ。さあ、私が見ている方向を貴女も見てみて下さい。きっと気に入ってもらえると思いますよ。」
「あら…それも、"確立的に"かしら?」
私は少々おどけた様な口調で言ってから、そのカメラが向いている方角に眼を向けた。するとそこには、真っ暗闇の只中に静かに佇む水色の球体があった。そのガラス球のような球体は暗闇しかない頭上の世界の中で、明らかに異色の存在であった。ゆっくりとした速度で表面の模様を不規則に変えてゆくその様はあまりにも美しすぎて、私は言葉を発する事が出来ず、息苦しくなるまで呼吸さえ忘れていた程だった。
「あれは、地球…よね。じゃあ、ここは…」
目の前の地球は青く輝いていた。私は目の前に広がる美しい光景と、頭の中で起こっている混乱の余り、再び声を出す事が出来なくなっていた。声の主はあの雑音を出す事なく、ただ静かに宙に浮かぶ地球をカメラで見詰めていた。
◆ ◆
暗闇に浮かぶガラス球を見続けてどれほど経ったのだろうか。声の主は再び雑音を立て始めた。
「先程、私が言った通り…貴女は元の世界に戻れます。」
「確立的にはでしょ?それは、どれくらい後の事なの?」
「もうすぐです。すぐに貴女は元の世界に戻ります。」
もうすぐ。私はその言葉に嬉しさを感じると思っていた。だが、実際はどうだったのだろうか。それは今でも分からない。ただ、もうすぐ声の主とお別れをしなくてはならないという事だけが、私には理解できていた。
「あなたは、ずっとここに居るの?」
「はい、ずっと、ここに居ます。」
「寂しくは…ないの?」
「はい、寂しくはありません。私は、今でも誰かの役に立っているのだと考えていますから。」
私の頭の中は、彼に聞きたい事ばかりで洪水になっていた。地球へは帰りたくないのか。こんな小さな乗り物で苦しくはないのか。一目、顔を見せてもらえないのか。そして、私の口から出た言葉は、ほんの些細な事だった。
「あなたの名前を教えてくれないかしら?」
その問いに声の主は雑音を立ててしばらく黙っていた。耳障りだった雑音は、何故か優しい吐息のように私には感じられた。そして、静かに声の主は口を開いた。
「私の名は、ルノホート…」
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・
・
目を開けると、そこにはいつもの景色が広がっていた。仄明るい洋灯の置かれた机、使い込まれたペン、無造作に置かれた本の山。今まで見ていた真っ白な世界などではなく、そこは紛れも無く図書館であった。
「パチュリー様、紅茶でも飲みますか?」
声が聞こえた方向を見ると、そこには大きな本を両手で抱えた小悪魔が微笑みながら立っていた。私は状況を把握できないままに、とりあえず小悪魔に紅茶を頼む事にした。
「はい、かしこまりました。では、すぐに用意いたしますね。」
その声はいつも聞いている優しい小悪魔の声。当たり前の事だが小悪魔の声には、あの時に聞いた耳障りな雑音が入っていなかった。
ふと、手元に目線を落とすと、そこには開いたままになった本が置いてあった。どうやら私は本を読んでいる時に寝てしまったらしい。私は一度大きく背伸びをすると、開きっぱなしにしたままの本を再び読み進める為に目を落とした。
ページの4分の1程度を使ってモノクロ写真が掲載されている項目を見て、私は懐かしさとも言うべき何かを感じていたのに気付いた。そしてあの時、夢の中で彼と見た美しいガラス球のような地球を思い出していた。彼は、まだあの場所で地球を見ているのだろうか。あの時と同じ場所でじっと動かないまま、優しい雑音を立てながら。
ロシア語で「月面を歩く者」という意味を持つ、ソビエト連邦により史上初めて月に送られた2機の無人機のうちの1機。ルノホート1号はルナ17号によって月に運ばれた、史上初の遠隔操作可能なロボットであって…
-終-