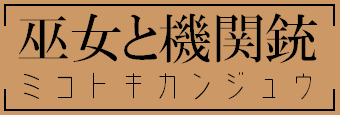短々編01 - 月の光と彼女の瞳
今宵も月は綺麗であった。暗闇に包まれた夜空に浮かんでいるその月には薄い雲が掛かり、微かな光を地上へと送っていた。月の光は地上を朧に照らしており、庭の石畳も草木も全てが青白く光っていた。館の庭に置かれた白いテーブルセットには、そんな月を静かに見つめている彼女が座っていた。彼女は何をする訳でも無く、何かを考えている訳でも無かった。ただひたすらに空を見上げ、冷たくも美しい光を送る月を見ているのであった。テーブルの上に置かれたカップの紅茶はとっくに冷めてしまっており、いかに長い間、彼女がそうしていたかを物語っていた。館の裏庭を心地良い微風が通り過ぎ、庭の木々が風に答えるように体を揺らして音を立てて、草の間にいる虫達は談笑をしているように賑やかに鳴いている。庭を風が通る度に、彼女の髪が月の光を浴びながら美しくなびくその様子は、彼女をいかに魅力的な姿に見せていた事だろうか。
「失礼いたします。風が冷たくなってきましたので、室内に入られた方が良いかと思いますが…」
彼女は後ろから聞こえてきた声にも振り向かず、ただ一心に月を見上げていた。そんな彼女を見て声を掛けた一人の妖精メイドは静かに下がろうとした。だが、机の上に冷えた紅茶の入ったカップが二つ並んでいるのを見つけ、片付ける事を思いついた。そして、誰も座っていない席に置かれたカップを下げようと手を触れた時、今まで微動だにしなかった彼女が口を開いた。
「レミィは何をしているの?」
メイドは返答をしようと彼女に視線を向けると、今まで月に向けていた彼女の紫色の瞳がしっかりとメイドを捕らえていた。彼女の瞳は月の光にも似た冷たい光を帯びていて、見るものを凍りつかせてしまうかのようであった。その瞳はじっと見ていると吸い込まれてしまいそうになるほどで、何かしらの魔力があるように思えた。メイドは必死に我を取り戻すと、努めて冷静な口調で返事をした。
「はい、お嬢様はメイド長と共に居間に居られると思います。」
その返答に、彼女はゆっくりと頷いて了承の意を表した。そして、再び頭上にじっと座っている月に視線を戻すと何も言わなくなってしまった。そこでメイドはカップを持ち、一礼をするとその場から離れる事にした。そのメイドには分からなかった。レミリアは自らの思った事などを口に出す。だが、彼女の場合はあまり口に出さないのだ。いつも難しそうな顔をして、何を考えているのか分からない。気まぐれで何を言い出すか分からないレミリアも怖いが、そのメイドにとっては彼女の方が恐ろしいような気がしてならなかった。
しばらくしてメイドは再びテラスへ戻ってくると、まだ同じ所に座っている彼女の姿を見つけた。ガラス戸越しに彼女の姿を見た瞬間、メイドははっと息を飲んだ。月明かりに照らされてじっと座っている彼女は美しくて、まるで神話に登場する女神のようでもあった。先程はそんな事など思いもしなかったはずなのに、何故そんな風に見えてしまったのだろうか。扉を一枚挟んで見る彼女は神々しくもあり、また禍々しくもあった。その相反する二つの印象が入り混じった妙なものが、メイドの目に焼きついていた。そして、気がつけばガラス戸に両手をつけてガラスケースの中の宝石を見入る子供のように彼女の後姿に見入っていたのだ。そのメイドには、彼女の後姿がひどく美しく見えた。ただそれだけの事なのだ。ただ、それだけの単純な事なのだ。そして、メイドは気付いた。自分は彼女を恐れている訳では無いのだと。彼女を恐れているのでは無く、彼女を畏れていたのだ。
月が先程より傾いていた。何処かで誰かの笑い声が聞こえた。そして、目の前には彼女が、ただ座っていた。何もせず、何も言わず、ただ月を眺めている。ただ、それだけなのだ。ただ、それだけだったのだ。
-終-