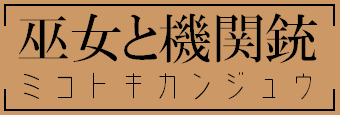混和は混濁の先に 前編
まったくもって暑い日だ。太陽の照り付ける中、箒に跨って空を飛ぶ魔理沙はそう思った。夏もそろそろ終わり頃だというのに、今年は嫌に残暑が厳しい。太陽が元気なのは良い事であるが、ちょっと元気過ぎるのではないだろうか。魔理沙は自らを暑く照らす太陽に対して愚痴をこぼしながら、ポケットから一枚の手紙を取り出した。几帳面なほど綺麗に三つ折にされたその手紙には、「図書館へ来てちょうだい。見せたいものがあるの。」とだけ書かれており、その下には達筆な字で図書館の主であるパチュリーの署名が入っていた。あのパチュリーから呼び出されるとは、珍しい事である。これは何か裏があるに違いない、と魔理沙は確信していた。しかし、暑い日で退屈していた魔理沙にとって、これ以上に無い暇潰しだった為、何かがあると分かっている上で飛び込む事にしたのであった。
霧の立ち込めた湖の水面を蹴って水飛沫を上げながら軽快に飛び越すと、そこは紅魔館であった。霧の中、突如として出現するその館は高く聳えるゴシック調の建物であり、大きな時計塔を備えた豪奢な館であった。しかし、その館の発するものはいかにも禍々しいといった空気であり、明るい光の存在など何処にも感じられない。今まで照り付けていた夏の暑い日差しも、この館に近づくにつれて勢いを失ってしまったかのように静かになっていた。しかし、そんな雰囲気にも魔理沙は、天然の冷房で良いじゃないかと全く気にする様子も無しに、館の正門を飛び越すと館の裏手に着地をした。そして、丁寧に隠されている古い鉄の扉を一枚開けると、そこは図書館へと続く狭い石階段であった。普通ならば降りるのを躊躇う程に暗く狭い階段であるが、既に通いなれている魔理沙はそんな事など微塵も思っていなかった。冷たい石の壁を手で辿りながら石階段を降りて行き、突当たりの扉を開けると空間が一気に開けた。周囲の薄暗い空間には書架が並び、その一つ一つに世界中の本がぎっしりと詰まっていた。 そこにある本の価値は計り知れないものがある。もしかすると外の世界に存在する、かの英国にある博物館や、米国の某大学付属図書館と同等、またはそれ以上かもしれない。
魔理沙がふと目の前に視線を落とすと、そこには小悪魔が立っていた。気配すら感じなかったが、今までずっと立っていたのだろうか。小悪魔は手に灯を点した燭台を持っており、何も言わずにじっと立っていた。仄明るい蝋燭の灯が、黙りこくった小悪魔の顔を不気味に照らし出しており、魔理沙を何やら不安にさせるのであった。あまりの沈黙に耐えかねた魔理沙が小悪魔に声をかけようとした瞬間、小悪魔は深々と一礼をすると仕草でついて来る様にと指示をした。雰囲気に圧倒された魔理沙は、黙って小悪魔について行くしかなかった。
暫く歩み続けていると、高く聳え立つ書架の間の通路に明かりが灯されているのが見えた。そこに近づくにつれて、それは円形のテーブルの上に灯された洋灯の明かりであるのが魔理沙には分かった。そして、そのテーブルの脇には柔らかそうなクッションを敷き詰めた椅子が二つ置いてあった。小悪魔は魔理沙に椅子の内の一つに座るよう勧めると、再び深々と一礼をして暗い通路へと消えていってしまった。魔理沙は仕方が無く椅子に腰をかけると、テーブルに置いてある洋灯のつまみを操作して弱くしか灯されていなかった明かりを強くした。ようやく明るくなった洋灯に照らされたテーブルの周りを見て、魔理沙は安堵の溜息を漏らしつつ椅子に深く座りなおした。
「ようこそ、良く来てくれたわね。魔理沙。」
暗闇から突如聞こえた声に身体を反射的に起こすと、魔理沙は辺りを見渡した。すると、ぼんやりとではあるが、こちらへ誰かが歩いてくるのが分かった。
「やあ、脅かさないでくれよ。今日はこういう趣向なのか?」
魔理沙には、近づいてくる足音と服のシルエットでそれが誰なのかが理解できていた。洋灯の灯りが、近づいてくる者の足から順に照らし出す姿は、何やら不気味な幽霊でも現れるかのようであったが、同時に幻術のようでもあった。
「いつも通りよ、魔理沙。いつも貴女は私の目を盗んで書物を持っていっているから、普段の私が分からないだけよ。」
声の主はテーブルに近づくと、持っていた本をテーブルの上にゆっくりと置いた。魔理沙はその本を見て不思議に思った。この本はいつも彼女が持ち歩いている本と違うではないか。彼女がいつも持っている本は、付箋がそこかしこに貼られていたはずだ。それに比べて、今日の本には付箋が付いていないし、何やら革の装丁が破れていたりして、ぼろぼろになっている。そして、黒革で装丁されているこの本には、厳重そうな鉄で出来た留め金が付いているのである。
「おい、パチェ。この本は何だ?やたらに古そうな本じゃないか。」
「これは、今研究している本よ。解読が難しいけど、中々面白い事が書いてあるわ。」
魔理沙は今にも朽ち果てそうな本を手に取ると、留め金の付いた重い表紙をめくって見た。
「これは…フォン・ユンツトの本じゃないか。しかも、ドイツ語の初版本だ…だけど、こんな狂人の書いた本を読んでどうするつもりなんだ?」
「確かに、ぱっと見ただけでは狂人の書いた文章にしか思えないわ。でもね、これを詳しく読み解くと、本当の意味が見えてくるはずなのよ…あとは、ユンツトが死ぬ間際に書いた草稿も読んでみたいのだけれど…あれは、読むのは不可能に近いわね。」
パチュリーは最後に、機会があったら貴女も読んでみたら、と付け加えると魔理沙の手から本を半ば無理やり引き抜いてテーブルの上に置きなおし、自らも空いている椅子に座った。そこで、やっと洋灯の灯がパチュリーの顔を照らし出した。パチュリーはいつも具合が悪そうな位に色白で、常に薄暗い所で本を読んでいるせいか眼を細めるのが癖になっているようであった。椅子に座ったパチュリーは魔理沙に、洋灯の灯を弱めても良いかと訪ねた。少々不審に思った魔理沙であったが断る必要も無いので承諾すると、パチュリーは洋灯の明かりを目一杯まで弱くしてしまった。そして、最近は明るい光がなおさら苦手になってしまって、と苦笑をしながら言うのだった。
「失礼いたします。お飲み物をお持ちいたしました。」
二人が他愛も無い話をしていると、小悪魔がワインボトルとグラスを二つ手に持って暗闇から現れた。小悪魔はグラスを二つテーブルに置くと、ワインのコルクを慣れた手つきで抜き始めた。小悪魔の手によってコルクはコルク抜きの針に貫かれ、ゆっくりとボトルから引き抜かれてゆく。そして、小気味良い音と共にコルクが抜けると、小悪魔はグラスにワインを注ぎ始めた。真っ赤な液体がグラスに満たされ、洋灯の明かりを反射しながら不気味に波を打っていた。小悪魔はボトルをテーブルに置くと、静かに暗闇の中へ消えていった。
「さあ、喉が渇いているでしょう?貴女が来るから用意しておいたのよ。」
小悪魔が立ち去ると、パチュリーは魔理沙にワインを勧めた。魔理沙は自らの目の前に置かれたグラスと手に取ると飲んでみる事にした。そのワインは、一口飲んだだけで良い物だと分かるほどで、味が非常に濃かった。ふとボトルを見ると、そのワインにはラベルが貼られておらず、何処で作られた物なのかも分からなかった。そこで、魔理沙はパチュリーに聞いてみる事にしたのであるが、その質問を聞くとパチュリーは不気味に微笑んで、レミィのワインセラーから盗んできたのだと答えるだけだった。
魔理沙は外が暑くて喉が渇いており、なおかつ目の前にあるワインが非常に美味しいので、あっという間にボトルの半分以上を一人で空けてしまっていた。それに対してパチュリーのグラスは先程から減っておらず、二口ほど口をつけただけのようであった。魔理沙が貪るようにワインを飲む姿を、パチュリーは少々気味の悪い笑顔を浮かべたまま、じっと見つめているのであった。
「ああ、そうだ…そういえば、この前…ここから、持っていった本の中で不気味なのがあったぜ。」
最後の一滴までボトルから搾り取るようにワインをグラスに注ぎながら魔理沙はパチュリーに言った。既にワインボトルを三本程ほぼ一人で空にしている魔理沙は酔いがかなり回っているらしく、顔は真っ赤で呂律が怪しくなっていたのだが、その一言をパチュリーは聞き逃さなかった。
「へえ…それは、どんな本なの?」
「えっと…確か、古くて…まあ、ここにある本は、全部古くて不気味なんだがな…うん、サラセンのなんとか…だったかな?そんな事が書いてあったぜ。」
「もしかして、それは…サラセンの暗黒祭祀の事じゃないかしら?英語で書かれた本でしょ?」
パチュリーの言葉を聞いて魔理沙は、それで間違いないと頷いた。
「掻い摘んで中を読んでみたけど、酷く不気味だったぜ…何かの翻訳本で、書いた人が自主規制かなんかで表現を原文から変えているみたいだったけどな…」
「私、あの本はあまり好きじゃないの。あれは訳者不明の翻訳本なのだけれど、翻訳した人間が修正を加えてしまっていて、正しい表現が読み取りにくいのよ。だから、私は元の文章を読むのが好きだわ。魔理沙、貴女は元の本を読んだ事がある?」
「原文は読んだ事が無い。翻訳した物であそこまで不気味なんだから元のやつなんて、相当ひどいんだろうな?」
パチュリーはまたもや不気味に微笑むと、手を挙げて小悪魔を呼んだ。そして、小悪魔に例の本とワインを持ってくるようにと指示をした。小悪魔が立ち去ると、パチュリーは魔理沙の方へ向き直ったが、魔理沙が何やらニヤニヤと笑いながら自分を見ているのにパチュリーは気付いた。そして、少々不快そうな表情を浮かべてパチュリーは魔理沙に言った。
「何よ、どうしたの?」
「いや、何だか…やっぱり、雰囲気がいつもと違うと思ってね。今日はどうしたんだ?」
「いつも通りよ、魔理沙。私はいつも通り。何も変な所なんて、無いわ。」
その一言に納得をしたのかしていないのか、魔理沙は椅子に寄り掛かると、私には違うように見えるけどね、と呟いた。
-続-