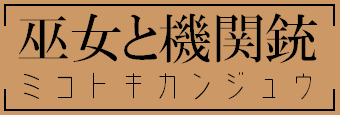混和は混濁の先に 後編
しばらくすると、小悪魔が本とワインボトルを持ってやって来た。小悪魔はボトルをテーブルの上に置くと、分厚く重そうな古い本をパチュリーに丁寧に手渡した。パチュリーは小悪魔に礼を述べ、下がらせると本を膝の上に置いて、魔理沙に手で軽く叩いて見せた。
「これが例の本の原本と言われている物で、著者はルートヴィヒ・プリン。装飾文字だから酷く読みにくいけど、魔術や呪術の資料としては素晴らしい本よ。」
魔理沙は興味津々にその本を眺めた。そして、装飾された文字で書かれている題名を読もうとしたが、それはパチュリーの手によって遮られてしまった。
「題名は知っているでしょう?英語翻訳版を持っていったのだから。ねえ、魔理沙?」
「ああ、そうかもしれないが…中々、その題名が思い出せないんだ…それに元々持っていくつもりの無かった本なんだぜ…?」
持って行くつもりも無かった本を何故、魔理沙は持っていったのか。それについて魔理沙は、近くの本を取った時に落ちたので、ついでに持って行ったのだとパチュリーに説明した。その説明をパチュリーはさらりと聞き流すと、魔理沙のグラスにワインを注いだ。
「じゃあ…その本の中で、アイラムの魔道士の話があったのは覚えているかしら?」
パチュリーはボトルをテーブルに置き、魔理沙が自らの言葉を飲み込むのを待った。そして、語を繋いだ。
「私はあの話に、すごく衝撃を受けたわ…そして、彼ら魔道士のやり方を実践できないかと試してみた事もあった。でも、残念な事に結果は望ましいものではなかった…」
やけに強いワインのせいなのだろうか、視界がぼやけて朦朧とし始めている魔理沙を尻目に、パチュリーは一人で淡々と喋り続けた。パチュリーは本を脇に置いて今まで座っていた椅子から立ち上がると、魔理沙の後ろへ回り、魔理沙の座っている椅子の背もたれに手をかけた。
「それからは、失敗した原因を突き止める為に様々な事をしたわ。でも、その原因というのがいたって単純なものだったのよ…そこで、貴女に協力してもらいたいの。どうかしら?貴女のように力のある魔法遣いなら、私の悩みを解決してくれると思うの。」
「でも、ちょっと待ってくれ…私は、何をしたら良いんだ…?」
気を抜くと何処かへ飛んでいきそうになる意識を必死に抑えながら話す魔理沙にパチュリーは静かに微笑むと、自らの腕を魔理沙の肩から胸へとゆっくりと沿わせてから、魔理沙を背後からしっかりと抱きしめた。そして、耳元でそっと囁くのである。
「貴女は何もしなくて良いわ。ただ、傍にいてくれれば…私の傍にいてくれれば、それで良いの。」
「どうしたんだよ…間違いなく、今日のパチェは変だぜ…」
「私が変?そうかもね…じゃあ、私がこうなったのは、誰のせいだと思う?」
魔理沙にはパチュリーの早くなった鼓動が、椅子の背もたれ越しにも伝わってくるように感じていた。パチュリーは少々汗ばんだ腕を魔理沙にしっかりと巻きつけ、息遣いは先程よりも荒くなっていた。パチュリーのその行為には今までの彼女には無かった、何やらぞっとする程の妖しいものを感じさせるところがあった。
「私は貴女の身体が欲しいわ。貴女の腕が、貴女の脚が、貴女の綺麗な眼が欲しいわ。その為には、貴女と私は一つにならなければならない…肉体的にも精神的にもね。」
息遣いがはっきりと聞こえる程に口を近づけて語りかけてくるパチュリーに、冗談はよせと言おうと魔理沙は口を開きかけた。しかし、魔理沙にはそれが出来なかった。なぜなら、魔理沙は膝の上に何かが落ちてきたのを感じて、それを見てしまったから。自らの膝の上に落ちていた物は白い何かであった。細長い小指程度の長さの何かが膝の上に散らばるように落ちていたのである。それを認識するまでに魔理沙はしばらくかかったが、それが何であるか分かった途端、魔理沙は思わずパチュリーの腕を振り払い椅子から飛ぶようにして立ち上がった。その時には、それまで魔理沙に纏わりつくようにしていたワインによる気だるさは一気に吹き飛んでしまっており、赤かった顔も蒼白に変わっていた。そして、眼は突如として訪れた恐怖に潤んでいた。
「パチェ…これは…何?いったい、何をしたんだ!?」
魔理沙は自らに降ってきた恐怖を追い払うように叫んだが、全身の震えが止まらないようであった。パチュリーは、そんな恐怖で歪む魔理沙の表情を楽しむように、背もたれにもたれ掛りながら見ていた。
「何を恐れているのかしら、魔理沙?さっきも言ったじゃない。これは、貴女と私が一つになる為に必要な事なのよ。恐れる必要は無いわ…貴女が振り払った子達は、全部、私の身体の一部よ。」
パチュリーの身体の一部。そんなはずは無い。魔理沙にはそれが信じられなかった。椅子や床の上に散らばるようにして落ちているその物体は、どう見ても蟲にしか見えなかったのだから。それは、白い大きな蛆であったのだ。そして、魔理沙は思い出した、あの時に持ち出した翻訳本の原本である、あまりにも恐ろしい本の事を。
「あの本の作者であるプリンは、旅の途中でとある魔道士と出会った。そして、その魔道士は何をしたのか…本を読んだ貴女なら解っているでしょう?」
「思い出した…そうだ、妖蛆の秘密だ!その中に記された、忌まわしいサラセン人の暗黒祭祀…それは、それは…おい、パチェ…冗談なら、もう止してくれよ…」
妖蛆の秘密。その本の事を全て思い出した魔理沙は、その名状しがたき恐ろしさから冷汗が止まらなくなっていた。そして、もう止めるようにパチュリーに対して必死に訴えたが、魔理沙の恐怖に震えた声はパチュリーに届いていないようであった。
「その魔道士は自らの身体を蟲に変えて、魂を若者の身体に移しかえたのよ…こうやって蟲達に変えて、ね。」
足元に転がる蟲達の中で、身の毛のよだつような薄気味悪い笑みを浮かべているパチュリーから魔理沙はあとずさった。そして、震える全身に力を込めると、おぼつかない足取りでパチュリーの目の前から逃げ去った。恐怖のあまり、魔理沙は叫び声を上げたくて堪らなかったが、何とか理性が勝ったらしく、叫びを抑えながら、やっとの思いで図書館から脱出する事が出来た。外の世界につながる鉄の扉を開けると、そこはいつもと変わらない世界であった。外ではもう夕暮れの時刻を迎えていて、世界は真っ赤に染まっていた。
暗い図書館の書架の影で、小悪魔は笑いを堪えるのに必死であった。魔理沙の普段は見られないような、尋常では無い脅え方を見ていると、ついつい笑い出してしまいそうで冷や冷やしたものだ。しかし、魔理沙のあの脅えようは、騙していて少々可哀想になってくる程でもあった。
「パチュリー様、彼女はどうやら図書館から出て行ったようですよ。」
小悪魔は書架の影から顔を出して、パチュリーに報告をした。それを聞くと、パチュリーは満足そうに頷いて、机の上の洋灯の明かりを少し強くした。
「演技をするって、肩が凝るわね…それに、いつもよりも薄暗くしていなければならなかったから、眼が悪くなりそうだったわ…」
「パチュリー様の演技、すごかったですよ…演技だと分かって見ている私も怖くなってくる位でしたもの。」
「ありがとう、こあ。でも、貴女も久々の悪戯で楽しかったんじゃないかしら?」
小悪魔はパチュリーの問いに、少々恥ずかしげに微笑みながら頷いた。
「それにしても、パチュリー様は中々に悪趣味な事を思いつくのですね…最近読んだ魔導書に面白そうな話があったから、これを使って魔理沙を驚かそうだなんて言い出すのですから。」
「いつも本を持っていかれているのだもの。これくらいの事をしたって、バチは当たらないでしょ?それに、もって行かれてばっかりじゃ…私だって、やっていられないわよ。」
だるそうに椅子に座ったパチュリーの脇を通りぬけ、小悪魔は床に散らばっている蟲を拾い集める為にしゃがみ込んだ。そして、蟲を一つずつ摘み上げると、素早く袋に投げ入れた。
「でも…この蟲、よく出来ていますよね…すごく不気味です。」
魔理沙の上に落とした蟲は本物ではなく、ただの良く出来た作り物であった。だが、相手がワインに酔って正常な判断の出来ない人間ならば、本物にしか見えない事だろう。
「袖に潜ませている間は、すごく気味が悪かったわ。偽物だって分かっているのにね…さてと、私は疲れたから少し休ませてもらうわ…こあ、悪いけど後片付けをよろしく。この本は元の所にしっかりと戻しておいて頂戴。」
パチュリーは小悪魔に片付けを頼むと、先ほど椅子の脇に置いた本を机の上に置いてから立ち上がった。机上の洋灯に照らされて、本の表紙に書かれている題名の装飾文字が怪しく輝きを放ち、その本からは何とも言い難い不吉な雰囲気が漂っていた。するとその時、パチュリーの袖から何かが床に落ちたのに小悪魔は気付いた。
「あ、パチュリー様。まだ蟲の模型が残っていたみたいですよ?」
小悪魔はパチュリーの足元まで行き、その落ちた蟲を拾った。だが、その蟲を拾い上げた瞬間、全身の毛が逆立つのを確かに感じた。今、小悪魔が拾った蟲は今までの蟲とは明らかに違う物だった。その蟲の感触は、手に伝わってくるものが妙に生々しかったのである。小悪魔は反射的に小さな叫び声を上げると、手に持っていた蟲を床に落とした。床に落ちた白い蛆は、身をよじりながら微かに蠢いていた。
「あらあら、出てきたら駄目なのに…まったく、困った子達ね…」
パチュリーは床に落ちて蠢いている蟲を拾い上げて、脅える小悪魔に微笑みかけると、音も無く暗闇の中へと消えていった。小悪魔の手には、あの蟲を触った時の恐ろしい感覚が消えずに残っていた。
-終-